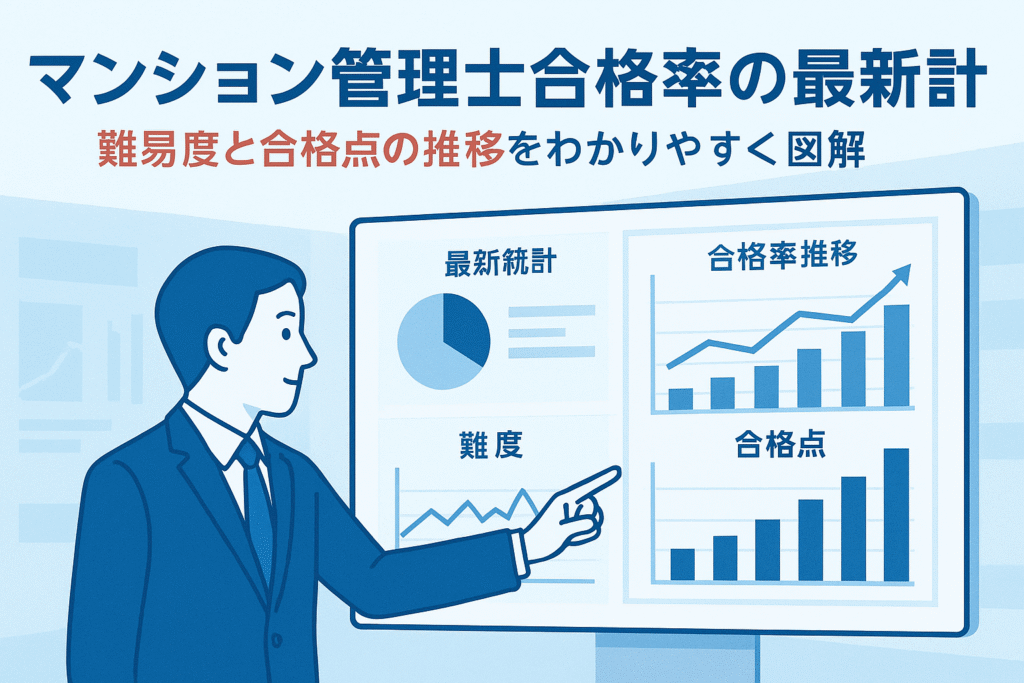マンション管理士試験の合格率を知っていますか?【令和6年度】の合格率は「12.7%」、受験者数は10,950人、合格者数は1,389人という非常に狭き門です。出題範囲も法令・民法・建築基準法など多岐にわたり、幅広い知識が求められるため難関資格と言われています。
「どれくらい勉強時間が必要なの?」「合格点は毎年変わるの?」「年齢や職業によって違いはあるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?実際、合格者の平均学習時間は300~400時間とも言われ、社会人の方や初学者には大きなハードルに感じやすい試験です。
ただし、推移グラフや地域・年齢別の分析から分かる通り、正しい戦略と準備を重ねれば合格も夢ではありません。本記事では、令和6年度最新データをもとに、合格率の背景や受験者層の変化、勉強法のポイントまで徹底的に解説します。
最後まで読むことで、合格への道筋とリアルな現状がクリアに見えてきます。まずは最新の合格率と受験者データから、その全貌を一緒に確認しましょう。
マンション管理士合格率は最新統計と推移|受験データを徹底解説
令和6年度マンション管理士試験の合格率・合格者数・受験者数
最新の令和6年度マンション管理士試験は、受験者数10,955人、合格者数1,389人、合格率は12.7%となりました。例年と比較し、合格率がやや高く出ています。この合格率は、50問中37問以上(5問免除者は45問中32問以上)の正答が合格基準でした。
マンション管理士試験は毎年11月下旬に実施され、結果は公益財団法人マンション管理センターから公表されます。資格取得希望者は難関とされますが、一部受験指導校では平均以上の合格率を記録しています。主な受験申込者は不動産・建築業界関係者が多いですが、管理業務主任者とのダブル受験や独学での合格も増えています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 10,955 | 1,389 | 12.7% |
| 令和5年 | 11,974 | 1,197 | 10.0% |
合格率は年度ごとに変動しますが、難易度は高い水準で維持されています。
過去10年間の合格率推移グラフと解説
過去10年のマンション管理士試験の合格率推移を見ると、7%から13%前後のレンジで推移しています。年度によって若干の上下はありますが、大きな変動は見られません。
合格率の推移が安定している理由は、出題範囲や試験制度が大きく変更されていないためです。合格基準点は受験者全体の成績分布をもとに相対評価で決定されるため、問題の難易度や受験者層の変化によって調整されます。管理業務主任者とのダブル受験増加や、社会人受験生の増加が合格率に一定の影響を与えていることも特徴です。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 令和6年 | 12.7% |
| 令和5年 | 10.0% |
| 令和4年 | 8.6% |
| 令和3年 | 9.0% |
| 令和2年 | 7.9% |
| 令和元年 | 8.0% |
| 平成30年 | 8.1% |
| 平成29年 | 8.2% |
| 平成28年 | 7.9% |
| 平成27年 | 8.0% |
この安定した合格率は、常に一定の難易度と質を保っている証といえます。
合格率の増減要因と受験者属性の変化
合格率の増減には複数の要因が影響しています。まず、受験者層の幅広さが挙げられ、近年は30~50代の社会人が中心です。中でも40代の合格率がやや高い傾向があり、これは現場経験や法令知識を活かしやすいからです。
また、ダブル受験や独学、通信講座(ユーキャン・アガルート・LECなど)利用者も増加しており、学習環境の多様化が進んでいます。都市部では不動産・マンション管理会社勤務者の受験が増え、男女比では男性受験者が多いものの女性比率も年々増加傾向です。
主な合格率増減の要因は次の通りです。
-
問題難易度の変化
-
受験者数や層の構成変化
-
管理業務主任者とのダブル受験効果
-
講座やテキストの充実化
-
5問免除制度利用の増加
近年ではこうした動向が合格率の微増にもつながっています。受験者の属性が多様化しつつあるため、より多角的な対策が重要です。
マンション管理士試験の難易度解析と合格率が低い具体的理由
出題科目の多面性と深さが及ぼす学習負担
マンション管理士試験は、法律・条例・建築基準法・区分所有法・民法など幅広い専門知識が求められます。さらにマンションの管理組合運営や維持管理、設備や修繕計画に関する実務の知見も問われるため、試験範囲は非常に多岐にわたります。これにより受験生には深い学習が求められ、短期間での合格が難しい試験といえます。
以下のテーブルは主な出題科目と内容例です。
| 科目 | 主な出題内容例 |
|---|---|
| 区分所有法 | 区分所有権、管理規約、管理組合法人 |
| 民法 | 財産権・担保物権・債権・契約の成立 |
| 建築基準法・設備 | 建築物の構造要件、エレベーター・給排水 |
| 管理組合の運営 | 総会開催、理事会運営、管理委託契約 |
| 維持管理・修繕計画 | 長期修繕計画、修繕積立金、トラブル対応 |
十分な学習計画を立て、各科目ごとに理解度を高めることが合格へのカギとなります。
受験資格の幅広さが合格率に及ぼす影響分析
マンション管理士試験は、年齢や学歴、職歴などに一切の受験資格制限がありません。そのため、さまざまなバックグラウンドの受験者が挑戦しており、初学者から経験者まで幅広い層が受験します。結果として、基礎知識が十分でない層の受験者が一定数含まれることとなり、合格率の低下に繋がっています。
主な受験者層は次のようになります。
-
不動産実務経験者
-
管理業務主任者や宅建士とのダブル受験者
-
独学・初学者
-
社会人・主婦・学生など多様な年代
この多様性が合格率の数値だけで試験の本質を判断しにくくしており、しっかりと対策をとった受験者にとっては突破の可能性も高まります。
合格点および相対評価方式の理解と合格率への影響
マンション管理士試験の合格点は、各年度の受験者全体の得点状況によって毎回変動する相対評価方式が採用されています。2024年は50点満点中37点(免除者は45点中32点)が合格点とされ、約12.7%が合格という実績が出ています。
-
相対評価のポイント
- 試験の難易度や全体の正答率に応じて合格基準が調整される
- 年による難易度の変動や問題ごとの難しさが合格率の推移に表れる
合格点の目安は例年7割程度が基準になりますが、実際には得点分布や年度ごとの問題傾向でも大きく左右されます。しっかりと過去問題分析や模試を活用し、相対評価を意識した受験対策が求められます。
合格点の推移と試験形式|相対評価の仕組みを徹底解説
合格点の年度別推移・最近の傾向
マンション管理士試験の合格点は、例年50点満点中34点から38点前後の範囲で変動しています。直近5年の合格点推移を見ると、合格ラインは難易度や受験者の平均点に合わせて毎年設定されているのが特徴です。自己採点で合格点以上を記録しても、正式には相対評価による最終決定が重要であり、油断は禁物です。
| 年度 | 合格点(50点満点) | 合格率(%) |
|---|---|---|
| 令和6年 | 37点 | 12.7 |
| 令和5年 | 38点 | 9.3 |
| 令和4年 | 36点 | 8.4 |
| 令和3年 | 36点 | 9.5 |
| 令和2年 | 36点 | 7.9 |
合格点は過去問や模試にも影響するため、年度ごとの推移を把握しておくことが戦略的な学習に直結します。特に2024年(令和6年)は例年より高めでした。
試験実施形式(問題数や免除科目ルール)
マンション管理士試験は、マークシート方式で全50問出題され、試験時間は2時間です。出題範囲は「法令」「管理組合運営」「建物設備」など多岐にわたります。また、「管理業務主任者」資格試験の合格者は5問免除となり、45問が採点対象となります。この5問免除制度は、ダブル受験や短期間での資格取得を目指す受験者にとって大きなメリットです。
制度の概要は以下の通りです。
| 受験区分 | 出題数 | 免除科目 | 合格点目安(例年) |
|---|---|---|---|
| 通常受験者 | 50問 | なし | 36~38点 |
| 5問免除受験者 | 45問 | 5問 | 32~34点 |
合格点は毎年変動しますが、管理業務主任者資格を活かす免除ルールやダブル受験は効率的な合格ルートとして定着しています。
合格ラインと点数分布・合否決定の難しさ
マンション管理士試験は相対評価を採用しており、受験者全体の得点分布を基に合格点が決定されます。したがって、試験が易しめの場合合格点が上がり、難しい年は下がる可能性があります。点数分布の中央値や標準偏差にも左右され、合否ボーダー付近の受験者が多いことも珍しくありません。
ポイントは以下の通りです。
-
合格率は例年7~13%
-
得点分布が偏ると競争が激化し、1点差で明暗が分かれる
-
合否決定は点数の高い順や特定の基準達成者によるもの
合格者数の上限や下限はありませんが、全体のレベルに応じた柔軟な判定が実施されます。合格を確実にするためには、毎年の傾向を読み取り、確実な得点戦略を立てることが非常に大切です。
免除制度の活用と合格率上昇の戦略的意義
5問免除制度の仕組みと申請条件の詳細
マンション管理士試験では、管理業務主任者資格の合格者に対して「5問免除制度」が設けられています。この制度を利用することで、本試験の50問中5問が免除され、実際の解答対象は45問となります。5問免除を受けるには、申込時に管理業務主任者の合格証明書を提出する必要があります。免除の対象となる科目は、重複する内容の基礎分野となります。
この制度は、管理業務主任者資格を取得済みの場合やダブル受験を目指す受験者にとって非常に有効です。免除された分の問題については自動的に正答扱いとなり、得点率を向上させるだけでなく、勉強範囲を効率的に絞り込むことが可能です。
申請時のポイントは以下の通りです。
-
管理業務主任者試験の合格者証の原本が必要
-
申請期限内に必要書類を提出が必須
-
免除は一人一回、同一年度は両資格を同時申請可能
免除制度利用者の合格率データ分析
5問免除制度を活用して受験した場合、通常受験者よりも合格率が高い傾向にあります。近年の統計データによると、免除制度利用者の合格率は通常のマンション管理士試験受験者と比較して平均2~3%高い実績を示しています。
下記のテーブルで詳細な比較を確認できます。
| 年度 | 全体合格率 | 5問免除者合格率 | 通常受験者合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 12.7% | 15.4% | 11.3% |
| 2023年 | 10.1% | 13.0% | 9.0% |
このように5問免除を利用した場合、解答数が減るため負担が軽減され、結果的に合格しやすくなります。複数の試験を経て知識や経験が高まっている点も、合格率向上の理由です。
合格率アップのための免除活用法と勉強計画例
免除制度を最大限に活用することで、効率よく合格を目指すことができます。まずは管理業務主任者から先に取得するか、またはダブル受験という戦略を立てるのが効果的です。勉強内容が重複する部分が多く、過去問演習で両試験対策を並行することで知識の定着率が高まります。
おすすめの勉強スケジュール例
- 前半2か月:基本テキストと映像講座で基礎固め
- 中盤3か月:過去問と模擬問題でアウトプットを徹底
- 後半1か月:5問免除分は復習に絞り、弱点分野を集中的に対策
メリットを活かすためにも、申請手続きを早期に済ませ、免除対象分野の勉強効率化を図ることが合格率を高めるポイントです。試験制度を正しく理解し、無駄のない戦略的な学習計画を実行することが成功への近道となります。
勉強法と時間管理|効率的学習で合格率を突破する秘訣
合格者アンケートに見る必要学習時間・平均学習負担
合格者の多くは300~400時間程度の学習時間を確保しています。働きながら受験する方が多く、平日は1~2時間、週末でまとめて進めるスタイルが主流です。下記は合格者アンケートを基にした平均的な学習プランの一例です。
| 学習期間 | 週あたり学習時間 | 合計時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 6か月 | 約12~16時間 | 約350時間 | 忙しい社会人に人気。短期集中がポイント |
| 9~12か月 | 約7~8時間 | 約350時間 | 無理なく継続、復習時間に余裕を持たせやすい |
効率アップの秘訣は日々の小さな積み重ねと、月ごと・週ごとの進捗管理にあります。学習時間が十分でも、内容をおろそかにすると合格は難しくなります。学習の質と継続が合格率アップのポイントです。
過去問題の取り組み方と模擬試験活用の効果
過去問題の活用は合格への近道です。出題傾向の把握や自分の弱点発見に最適で、合格者のほぼ全員が5年分以上の過去問を繰り返し解いています。
効果的な取り組み方
- 問題を解く前にテキストで該当範囲を復習
- 過去5年分を3周以上繰り返す
- 間違えた問題は必ず解説を確認する
- 模擬試験は本番同様の制限時間で実施
模擬試験は本番の時間感覚やプレッシャーに慣れるのに役立ち、時間配分や合否ラインの感覚も養えます。予備校の公開模試も大いに活用するとよいでしょう。
予備校利用、独学、通信講座の合格率比較・選び方
各学習スタイルで実際の合格率や特徴が異なります。自分のライフスタイルや習熟度に応じた選択が、最短合格のカギです。
| 学習スタイル | 合格率の目安 | 特徴・強み |
|---|---|---|
| 予備校(通学) | 約35~42% | サポート充実、強制力あり。指導と質疑がリアルタイム |
| 通信講座 | 約15~30% | 映像・テキスト両対応。自分のペースで進めやすい |
| 独学 | 約8~12% | コストパフォーマンス抜群。自己管理力が必須 |
【ポイント】
-
予備校利用者は短期間で高得点を目指しやすい
-
通信講座は教材のわかりやすさやサポートの評判をチェック
-
独学はスケジュール管理や質問対応の仕組みを工夫することでカバー
合格率を左右するのは勉強スタイルの選択のみならず、自分に合ったやり方を見つけて継続できるかどうかが重要です。
合格者の属性と試験傾向|年代別・地域別の実態解説
合格者の年齢層別比率と傾向動向
マンション管理士試験の合格者は、幅広い年齢層に分布していることが特徴です。近年の合格者データでは、30代・40代・50代がボリュームゾーンとなっており、とくに40代が最も多い傾向が見られます。社会経験や不動産に関する知識を持つ受験者の受験が多く、キャリアアップや転職目的で資格を取得する人が多いのが特徴です。
合格者の年齢層ごとの割合を一覧にまとめました。
| 年齢層 | 割合(目安) |
|---|---|
| 20代 | 約8% |
| 30代 | 約22% |
| 40代 | 約33% |
| 50代 | 約25% |
| 60代以上 | 約12% |
年齢が上がるにつれて受験者数は減少しますが、60代・70代でも毎年一定数の合格者がいることがこの資格の特徴です。
地域別の受験動向と合格率差異
マンション管理士試験は全国各地で実施されていますが、地域によって受験者数と合格率に差が出る傾向があります。都市部ではマンション数が多いこともあり、受験者数が特に多くなっています。以下に主な都市圏と地方の受験傾向・特徴を比較します。
| 地域 | 受験者数の傾向 | 合格率の特徴 |
|---|---|---|
| 東京圏 | 非常に多い | 全国平均に近い |
| 大阪圏 | 多い | やや高め |
| 名古屋 | 平均程度 | 全国平均に近い |
| 地方都市 | 少ない | やや低め〜平均 |
都市部の方が勉強環境や講座受講の機会も多く、合格率が安定しやすい一方、地方では独学受験が中心で合格率もやや低めになることがあります。ただし、どの地域でも熱意を持って学習を継続することで十分な合格が可能です。
合格者の職業・経歴背景別傾向分析
マンション管理士合格者は、不動産業界や建築業界出身者が多い一方で、異業種からの合格事例も増加しています。主な職業別・経歴別の傾向は以下の通りです。
-
不動産仲介・管理業務の従事者
-
建築・設備関連の技術者
-
行政書士・宅建士等の有資格者
-
企業の管理部門や法務職
-
主婦や定年退職後のセカンドキャリア希望者
近年はダブルライセンス(宅建士・管理業務主任者との併用)取得者も多く、資格を活かした転職や副業を目指すケースが増えています。基礎知識がなくても学習の工夫や効率的な対策で合格を目指せるため、多様なバックグラウンドの方に門戸が開かれている資格です。
マンション管理士資格の価値と合格後の仕事・年収事情
主な就職・転職先と業務内容の実態
マンション管理士資格は、マンション管理組合のコンサルタントや、管理会社、建設会社、設計事務所、不動産会社など、幅広い分野で活かせます。主な勤務先とその業務内容を下表にまとめました。
| 勤務先 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 管理組合(会計/理事) | 管理規約改正、長期修繕計画支援、総会対応 |
| 管理会社・不動産会社 | 法令相談、登記補助、建物管理全般 |
| 建設・設備関連会社 | 技術相談、設備更新アドバイス |
| 独立事務所 | 個人コンサル、調停・相談対応、研修講師 |
強みは管理規約・建物維持などの法律知識を生かし、所有者や管理組合の課題を解決できる点。近年は高経年マンション増加により、管理士のニーズも年々高まっています。
平均的な収入水準と高収入事例紹介
マンション管理士の平均年収は300~600万円程度が一般的ですが、経験や実績によって上限は大きく変動します。
-
一般的な年収レンジ:300万円~600万円
-
管理会社等の正社員:年収350万円前後からスタート
-
経験・資格・ポジションにより、700万円超も目指せる
-
独立開業後、案件獲得数や講師・出版活動で年収1000万円以上となるケースも
下記の年収分布表が参考になります(目安)。
| ポジション | 年収目安 |
|---|---|
| 管理会社社員 | 350~500万円 |
| 組合顧問 | 400~800万円 |
| 独立(多数受託) | 800万円超 |
保有資格や業務内容、地域、市場ニーズにより大きな差がありますが、専門性を高めることで収入アップが可能です。
資格の独立開業可能性と副業展望
資格取得後は独立開業も現実的な選択肢です。管理組合からの直接相談や第三者管理者業務、各種コンサル業務を受託できます。
-
独立で役立つ業務例
- 管理規約の見直しアドバイス
- 大規模修繕計画のコンサル
- 管理費削減やトラブル解決
- 民事調停、不動産関連講座の講師業務
副業としても比較的参入しやすく、特に不動産・建設・法律分野の知識と親和性が高い点は大きなメリットです。近年はAIやIT活用により相談の幅も広がっています。
自身の経験や強みを活かすことで、安定した収入を得ながらステップアップや新規ビジネスに挑戦することも可能です。
管理業務主任者・宅建士との比較とダブル受験最新動向
各資格の合格率・試験難易度客観比較
マンション管理士と管理業務主任者、宅建士の合格率や試験難易度には大きな違いがあります。
| 資格名 | 合格率(最新傾向) | 試験難易度 | 主な業務範囲 |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 約12.7% | 難関 | 管理組合の運営とアドバイス |
| 管理業務主任者 | 約20% | 中程度 | 管理契約の重要事項説明 任務 |
| 宅地建物取引士(宅建士) | 約17% | 普通~やや難 | 不動産取引の重要事項説明 |
マンション管理士は試験範囲が広く、出題の専門性や難易度が高い点が特徴です。管理業務主任者や宅建士に比べて記憶だけでなく深い理解と応用力が問われるため、合格率も低い傾向です。
ダブル受験のメリット・効率的な学習方法
管理業務主任者とマンション管理士のダブル受験は効率的な資格取得を狙う方におすすめです。両試験の出題範囲には共通部分が多く、学習内容を重複させ効率を上げることができます。
ダブル受験の主なメリット
-
短期間で2つの国家資格取得を目指せる
-
勉強時間やテキスト代を節約できる
-
合格後のキャリア選択肢が広がる
効率的な学習方法
-
共通分野(民法・区分所有法・規約管理)を集中的にマスターする
-
応用力が必要なマンション管理士対策には過去問演習を重視する
-
管理業務主任者受験を先に行い、合格後に5問免除制度を活用する
二資格を比較しながら学ぶことで、長期的なキャリア設計及び資格取得のモチベーション維持にも役立ちます。
それぞれの資格の活用事例とキャリアパス
それぞれの資格は取得後に活躍できる分野が明確に異なります。
マンション管理士の活用例
-
分譲マンション管理会社で管理組合の相談役として活躍
-
独立開業して顧問やコンサルティング業に従事
-
管理組合の理事やアドバイザーとして問題解決に貢献
管理業務主任者の活用例
-
マンション管理会社で契約や重要事項説明を担当
-
大手不動産グループの管理部門でのキャリア構築
-
管理現場の責任者・マネージャーとして活躍
宅建士の活用例
-
不動産取引や営業、仲介業務全般で必須資格
-
不動産会社勤務、独立事務所運営
-
営業部門のリーダーや管理職
キャリアパスに活かすポイント
-
ダブル・トリプル資格の取得で年収アップや管理職、独立開業につながる
-
業務範囲の違いを理解し、自身の希望に沿った職種を選べる
-
不動産業界・管理業界での信頼性や専門性が強化される
それぞれの資格ごとに業界内で求められる役割や活用される場面が異なるため、将来設計に合わせた資格取得戦略が重要となります。
受験生が抱える疑問をプロが回答|マンション管理士合格率にまつわるQ&A
マンション管理士合格率はなぜ低いのか?
マンション管理士試験の合格率はおよそ7%~13%前後と、国家資格の中でも特に低い水準にあります。その理由は試験範囲が広く、法律・建築・管理業務など多岐にわたる専門知識を問われるためです。さらに、多くの受験者が独学で対策することも合格率が低い背景に挙げられます。最近の合格率推移を見ると、2024年(令和6年)は12.7%とやや高めですが、依然として難易度は高めです。以下、合格率が低い主な理由をまとめました。
-
出題範囲が広く専門的な知識を要する
-
問題文の難解さと実務重視の内容
-
管理業務主任者とダブルで受験する方が多い
-
相対評価により毎年合格基準が変動する
試験勉強にかかる平均時間はどのくらい?
マンション管理士試験に合格するためには、一般的に300~400時間ほどの学習時間が必要とされています。もちろん受験経験や関連資格(宅建士・管理業務主任者など)の有無、基礎知識によって異なりますが、初学者の場合は半年から1年間、継続的な学習が求められることが多いです。独学合格者も多数いますが、効率性やモチベーション維持の観点では通信講座(ユーキャン・アガルート・LECなど)の活用も有効な方法です。
学習スケジュール例
-
1日1~2時間 × 週5日学習 → 6~8か月で到達可能
-
模試や過去問演習を併用し、弱点を重点復習
マンション管理士と宅建士、どちらが難しい?
マンション管理士と宅建士はともに不動産分野の国家資格ですが、内容や難易度に顕著な違いがあります。一般的に合格率だけを見るとマンション管理士の方が難関とされています。宅建士の合格率は約15~18%とやや高めで、マンション管理士の方が試験範囲が広く実務寄りであるため、難易度も高いです。
| 資格 | 合格率 | 主な試験範囲 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 7~13% | 法律、建築、管理業務 | 高い |
| 宅建士 | 15~18% | 宅建業法、民法、不動産取引 | 比較的取りやすい |
資格取得で期待できる年収やキャリアは?
マンション管理士資格を取得すると、独占業務自体はありませんが、マンション管理組合へのコンサルタント業務や管理会社での昇進・転職、独立開業など多彩なキャリアの選択肢が広がります。年収は勤務先や業務内容によって異なりますが、一般的な管理会社勤務では年収350万~600万円が目安です。副業や独立コンサルタントとして活動する方も多く、経験次第で年収1000万円を超えるケースも実際にあります。
-
管理会社でのキャリアアップ
-
マンション管理組合への専門助言
-
ダブル資格取得による転職・独立も可能
試験の合格点や合格基準は?
マンション管理士試験の合格基準は相対評価方式を採用しています。令和6年(2024年)の試験では、50問中37点が合格ラインとなっており、過去数年の推移も35~38点程度です。ただし受験者全体の得点分布によって毎年調整されるため、一律ではありません。また、管理業務主任者試験合格者には5問免除制度があり、免除者は45問中32点程度が目安となっています。
合格点の特徴
-
毎年の受験状況や難易度に応じて変動
-
一定の高得点を保つ必要がある
-
5問免除制度を上手く活用する受験者も多数
合格を目指すためには、相対評価を踏まえた全体の得点力アップと、過去問をしっかり分析する戦略が重要です。