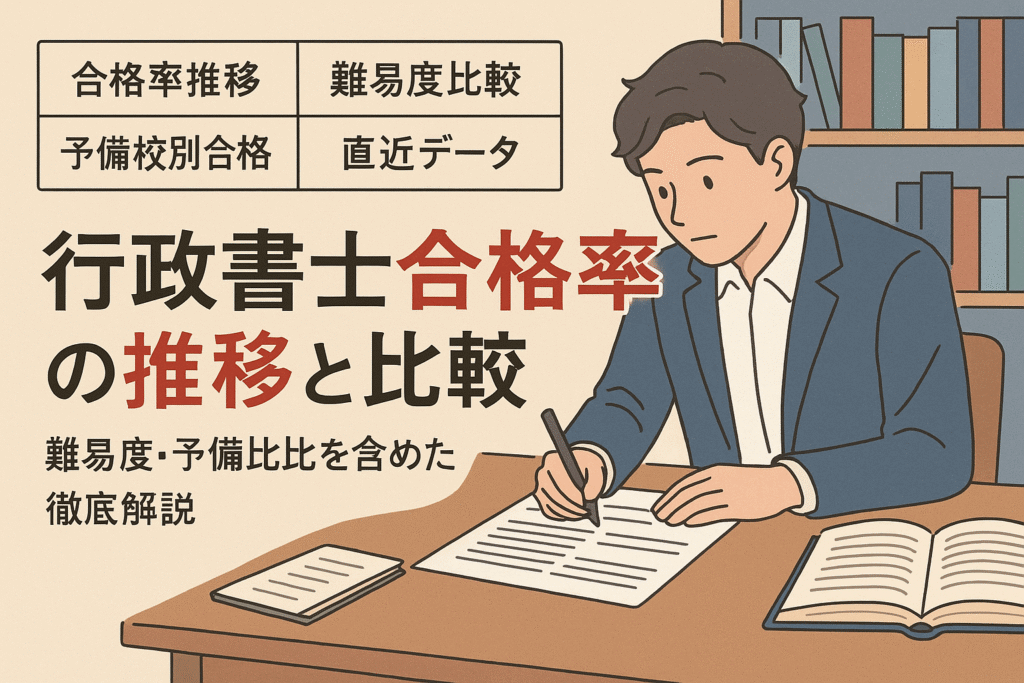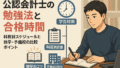「行政書士の合格率はどれくらいなのか?」と気になっていませんか。
【令和6年度(2024年)】行政書士試験の合格率は13.1%。受験者数42,542人のうち、合格者は5,576人と、毎年高い壁がそびえ立っています。特に、独学者や初学者が多い中で、この数字を突破する難しさを実感している方も少なくありません。
厳しい合格率の背景には、年度ごとの合格基準点の調整や記述式採点の厳格化があります。また、近年では法改正や出題傾向の変動も影響し、単なる暗記だけでは太刀打ちできない試験へと進化しました。「なぜ合格率が変動するのか?」、「過去10年でどんな推移があるのか?」といった疑問を持つ方も多いはずです。
このページでは最新の公式データと数十年分の合格率推移、他資格との難易度比較、さらに合格者属性まで、徹底的に分析。受験生が直面する本当の壁と合格への具体的アプローチまで明らかにします。
【今の学習法で本当に合格できるのか…】と不安な方も、現実を正しく知ることが、第一歩です。最後まで読み進めれば、「今何をすべきか」が見えてきます。
行政書士合格率を最新データと詳細分析から徹底解説
令和6年度(2024年度)行政書士合格率の数値詳細―受験年度ごとの合格率に注目し、最新の試験データを網羅
2024年度の行政書士試験は、受験者数、合格者数、そして合格率という3つの公的データが注目されています。直近の公式発表によると、令和6年度の受験者数は46,084人、合格者数は5,955人、合格率は12.9%でした。この合格率は例年と比べてほぼ平均的な数値となっており、近年10%台前半で推移する傾向が続いています。また、法学部だけでなく多様な学歴や年齢層の受験が特徴的です。下記は年度ごとの合格率および関連データの比較です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 47,870 | 6,104 | 12.8% |
| 令和6年 | 46,084 | 5,955 | 12.9% |
受験者数・合格者数・合格率の公的データを完全網羅―信頼できる数字の根拠から全体像を把握
行政書士試験では、実際の合格率や受験者数・合格者数の推移を正確に把握することが大切です。令和6年度は、前年から約1,800人の受験者減少が見られましたが、合格率自体は微増しています。この背景には、受験対策の多様化や通信教育など新たな勉強法の浸透が関係しています。合格率データに加えて、行政書士合格発表や合格発表から資格登録までの流れも知識として押さえておきたいポイントです。信頼できる情報源を元にした数字で本試験の全体像を掴みましょう。
令和6年度合格率の前年比較と要因分析―合格率変動の主な要因をわかりやすく解説
行政書士合格率は毎年わずかな変動が見られます。令和5年と6年では受験者数が減少している一方、合格率は0.1%上昇しています。主な要因としては法律分野の基礎知識を問う出題傾向の強化、問題の難易度水準の維持、予備校などで養われる実践対策力がポイントと考えられます。特に最近は独学でも高い合格率を叩き出すケースが増えています。受験生の学習スタイルや勉強時間の確保が直接的に合格率へ反映され始めているのが現状です。
過去10年〜昭和期までの行政書士合格率推移と特徴―長期間にわたる合格率の推移をデータで解説
行政書士試験は法改正や時代背景によって合格率が大きく変動してきました。平成、令和、昭和を通じて見てみると、特に制度改正時や社会的な需要変化が合格率推移に影響しています。ここ10年は10~15%で落ち着いていますが、昭和期には20%を超える年もありました。長期スパンで合格率を一覧できる下記データも参考になります。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 昭和末期 | 20%前後 |
| 平成初期 | 15%~25% |
| 平成後期 | 8%~12% |
| 令和元年 | 11.5% |
| 令和5年 | 12.8% |
| 令和6年 | 12.9% |
昭和から令和までの長期推移データの解説―時代ごとの合格率と背景の変遷を詳しく説明
行政書士試験は昭和時代には合格率が高い傾向にあり、20%を超える年も多く存在しました。一方、平成に入ると受験者層の拡大や法令知識の厳格化で難易度が上がり、合格率は大きく低下。その後、試験制度が安定し受験対策のノウハウが広まったことで、近年は安定して10%台前半の合格率を維持しています。背景として法改正、社会人受験者の増加、通学・通信スクールの普及が大きく影響しています。
合格率変動に影響を与えた社会的・制度的背景―制度や社会情勢が試験や合格率に及ぼす影響を深堀り
行政書士合格率の変動には複数の社会的・制度的要素が色濃く影響します。たとえば、バブル崩壊や就職氷河期には社会人受験者が急増し、受験者数が大きく伸びました。また、出題科目や合格基準の改定がなされるたびに一時的な合格率の上下が繰り返されています。近年では、働き方改革や副業需要の高まりによる資格人気、法改正に伴う行政知識の重要性増大も顕著です。こうした環境の変化が、行政書士資格と合格率の両面を動かしています。
行政書士合格率の難易度構造と他資格との比較分析
行政書士試験の出題形式と難易度要因の詳細―出題内容や配点、近年の傾向をわかりやすく整理
行政書士試験は法令科目と一般知識科目に分かれています。法令科目では憲法・行政法・民法などが出題され、一般知識科目では現代社会や情報通信、文章理解など幅広い分野から出題されます。近年は法改正に対応した配点や、応用力を問う問題が増加している点が特徴です。
下記のテーブルは主要な出題科目と配点の目安です。
| 出題科目 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 憲法 | 5 | 20 |
| 行政法 | 19 | 76 |
| 民法 | 9 | 36 |
| 商法・会社法 | 5 | 20 |
| 一般知識 | 14 | 56 |
| 記述式問題 | 3 | 60 |
全体で300点満点中、180点以上が合格基準です。
出題傾向としては、法令科目の比重が高く、正確な知識とスピードが求められます。一般知識科目でも足切り(基準点未満で不合格)があるため、バランスの良い対策が必要です。
科目別難易度と合格基準点の影響―科目ごとに異なる難易度や合格基準の仕組み
各科目の難易度にはばらつきがあります。行政法や民法は出題数が多く、得点源ですが、条文や判例の細かい知識が要求されます。記述式問題は部分点の加算がありつつも、多くの受験生が苦手とする分野です。
合格基準点は総合180点以上で、かつ法令科目244点中122点以上、一般知識科目56点中24点以上という基準が設けられています。特に一般知識は配点が低いわりに足切り制度があるため、1科目の不得意が合否に直結するケースも多いです。
法学部出身でも油断できず、独学で効率的な学習と正答力向上が欠かせません。学習塾や通信講座のサポートを活用する受験生も増加する傾向です。
宅建や司法書士など他国家資格との合格率比較―他資格とどのような違いや優位性があるか
行政書士試験の合格率は近年12%前後で推移していますが、他資格と比べてどうでしょうか。下記のテーブルで代表的な資格と比較します。
| 資格 | 直近合格率 | 受験者数 | 主な受験者層 |
|---|---|---|---|
| 行政書士 | 12.9% | 約40,000人 | 法学部生・社会人・主婦等 |
| 宅建 | 17.2% | 約200,000人以上 | 不動産業界・一般社会人 |
| 司法書士 | 4% | 約30,000人 | 法律専門志向 |
行政書士は宅建より低く、司法書士より高い合格率で、初心者から社会人、幅広い受験者層が挑戦しやすいのが特徴です。宅建は比較的短期間の対策で合格可能ですが、行政書士は法令の深い知識や文章理解力も要求されるため、計画的な学習がポイントとなります。
合格率数値の背景にある資格特性の違い―数字だけでなく資格ごとの背景まで詳細解説
合格率の数値だけを見ると行政書士は中間程度に位置しますが、資格ごとに性格や受験事情が異なります。
- 行政書士は学歴・年齢を問わず受験可能で、法務・行政分野への転職や独立開業を目指す人が多いです。幅広い層が受験できる反面、試験形式は多面的なので総合力が問われます。
- 宅建士は主に不動産業界で必須資格となるため、社会人リスキリングやキャリアアップ目的の受験者が目立ち、短期間での取得ニーズが高いです。
- 司法書士はより高度な専門資格として扱われ、法学部偏差値65相当の学力や長期間の学習が必要とされます。合格率が低い分、専門性や希少性が高く、年収や就職にも強く影響します。
独学でも行政書士の合格は可能ですが、効率的な勉強法や予備校・通信講座の利用で合格率を高めるケースが多くなっています。合格後は行政書士事務所開設や企業法務への道などキャリア展望も広がり、合格の価値が高い資格といえるでしょう。
行政書士合格率にかかる科目別合格基準点・記述採点の実態と影響
行政書士合格基準点の年度ごとの推移と傾向―年度ごとに変化する基準点の現実と合格率の関連
行政書士試験では、科目別合格基準点が定められており、合格率の推移にも大きく関わっています。毎年の合格率は10%前後で推移していますが、これは年度ごとに細かく設定される基準点による影響が大きいです。法令科目、一般知識科目、記述式といった各セクションごとに足切りラインがあり、この基準を突破できなければトータルの点数に関係なく不合格となる仕組みです。
下記は主な年度ごとの基準点と合格率推移例です。
| 年度 | 合格率 | 科目別基準点(法令等) | 科目別基準点(一般知識) | 記述式配点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 12.9% | 122/244点 | 24/56点 | 60/300点 |
| 令和5年 | 13.98% | 122/244点 | 24/56点 | 60/300点 |
| 令和4年 | 13.1% | 122/244点 | 24/56点 | 60/300点 |
基準点が高めに設定される年度ほど合格率はやや低下し、絶対評価であるため年度ごとの出題難易度や採点基準が合格者数に直結します。
足切り基準や記述式採点の厳しさに関する最新動向―記述処理や基準点の現代的な厳しさを分析
行政書士試験では、足切り基準による不合格者が毎年一定数発生します。特に一般知識分野は24点(例年8問正解相当)が基準となるため、得意不得意が明暗を分けやすい項目といえます。
また、記述式問題の採点は「正確性」「論理性」「キーワードの適切な使用」など多面的な観点から評価され、不正確な答案や論旨がずれている場合は減点対象となります。記述の配点比重が高いことで、マークシートのみで合格する戦略は難しくなり、近年の行政書士試験は論述力と幅広い知識が求められています。
足切りラインに到達しつつ、記述式でしっかり得点する必要があり、これが「行政書士合格率推移」や「行政書士合格率低い理由」の核心となっています。
- 足切り点突破が最初のハードル
- 記述抜きではほぼ合格不可能
- 毎年微妙な基準変更が行われることも
合格基準点が合格率に及ぼす具体的な影響分析―合格者選定への直接的なインパクトに着目
合格基準点は行政書士試験の合格率そのものに直結しています。トータルで180点以上(300点満点)かつ各分野の基準点クリアという絶対的なルールです。この基準を満たせないケースが多いため、実際には「行政書士誰でも受かる」わけではなく、計画的な学習の重要性が強調される理由となります。
主なインパクトは以下の通りです。
- 難問・奇問対策: 証拠力の高い基礎・頻出論点を落とさなければ、合格が近づきます
- 科目バランス必須: 得点源となりやすい法令科目でも安心できず、一般知識や記述の対策が欠かせません
- 予備校活用のメリット: 最新の基準や出題傾向情報をキャッチしやすく、記述添削も充実
合格基準点の存在が、単なる点数獲得型ではなく総合力勝負の試験であることを示しており、これが毎年の「行政書士合格率推移」や「行政書士合格率高い学校」といった比較にも強い影響を与えています。合格発表では「行政書士 合格率 2024」「行政書士 合格率 2025」といった年度別の話題が上位を占め、基準点・採点傾向への注目は今後も高まるでしょう。
行政書士合格率に見る受験者属性と合格者の実態データ分析
年齢層・学歴・受験歴別の合格率詳細―合格者の多様な属性データを使い分けて紹介
行政書士試験の合格者は幅広い年齢やさまざまな学歴層に分布しています。以下のテーブルは、年代ごとの合格者割合や受験歴別の特性を分かりやすくまとめたものです。
| 属性 | 合格者割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 20代 | 約25% | 法学部出身者が多く、知識の新しさを活かして効率的に合格 |
| 30代 | 約30% | 働きながらキャリアアップを目指す社会人の挑戦が目立つ |
| 40代以上 | 約40% | 現場経験や再挑戦組が多く、計画的な学習で合格 |
| 大学生 | 約15% | 時間を活かし集中して学習する傾向 |
| 初学者 | 約45% (推計) | 法律未経験者も多数、しっかり学べば合格を狙える |
| 複数回受験者 | 約60% | 過去の経験を活かしてリベンジ成功する例が多い |
ポイント
- 幅広い年齢と多様なバックグラウンドが特徴
- 複数回受験者の割合が高く、積み重ねが結果につながっている
合格者の平均年齢・年代別合格率の深掘り―年代ごとの合格しやすさや傾向
行政書士試験では、20〜40代はもちろん、60代以上の合格者も毎年一定数存在します。平均年齢は約37歳で、社会経験を積んだ方の挑戦が目立ちます。年代別の主な傾向は以下の通りです。
- 20代〜30代
- 専門知識の習得スピードが速く、短期集中型の合格がめだつ
- 法学系大学出身者が有利だが、未経験者も十分にチャンスあり
- 40代〜50代
- 社会人経験を活かした学習方法と、実務目線での理解が強み
- 計画的な時間管理が勝敗を分ける
- 60代以上
- マイペースな学習が許されるリタイア世代の受験も増加
- 「学び直し」やセカンドキャリアを意識する方が多い
このように、年齢を問わず挑戦できる試験である点が大きな特長です。
大学生・初学者・独学者の合格率と傾向分析―初心者や独学者のリアルな合格実態
大学生や初学者でも行政書士試験の合格は十分に可能です。特に近年は独学者の合格事例も増加しています。
| 分類 | 合格率(目安) | 傾向/特徴 |
|---|---|---|
| 大学生 | 約10~15% | 本業の学業と両立しやすく、計画的な学習で成果を上げる |
| 初学者 | 約10% | 適切な教材と情報収集で効率良く力を伸ばす人が多い |
| 独学者 | 7~12%程度 | インターネットや市販教材を徹底活用し、自己管理で合格する傾向 |
注目ポイント
- 予備校や講座利用者は合格率がさらに高い傾向
- SNSやネット掲示板の情報活用で、独学者も自分に合った勉強法を模索
初心者でも計画的に学べば合格は十分に目指せます。
受験者数推移と受験動機の社会的背景―市場規模や受験理由の分析
近年、行政書士試験の受験者数は年ごとに変動を見せています。直近年度の受験者は例年約3万5千人前後で推移し、社会の変化とともにその動機も多様化しています。
受験動機の主な特徴
- 転職やキャリアアップのため
- 法律知識の習得や自己研鑽目的
- 開業を視野に入れた独立志向
- 社会人・主婦・退職後の生涯学習志向
受験者数の推移は、景気や社会状況とも関連し、資格の市場価値に大きな注目が集まっています。行政書士の年収や出身大学ランキング、偏差値レベルなども合格後のキャリア設計に影響を与えているため、受験動機はますます多様化しています。
合格率が高い行政書士予備校・通信講座を詳細比較
主要予備校(伊藤塾、TAC、アガルート、スタディング等)の合格率比較―受験対策校それぞれの合格率・特色の比較
行政書士試験における主要予備校の実績や特色を比較することで、学習方法選びの精度を高めることができます。下記では、代表的な行政書士試験対策校の合格率に関する動向やカリキュラムの違いを表でまとめています。
| 予備校 | 合格率目安 | 特色 |
|---|---|---|
| 伊藤塾 | 非公開だが実績高い | 合格体験記多数、基礎から応用まで段階的なカリキュラム |
| TAC | 非公開 | 法学部出身者・未経験者両対応カリキュラム、課題添削や模試が充実 |
| アガルートアカデミー | 39.3%(公式発表) | 合格者数公表、映像講義とフォロー体制が強み |
| スタディング | 非公開 | コスパに優れた通信学習、スマホ対応教材・自動復習システム |
特徴的なポイント
- アガルートは合格率を公式発表しており、39.3%と業界内でも高水準
- タイプ別で適したコース設計やサポート体制が展開されている
- 合格率公表の有無や学習サポートの質の違いに注目するのがおすすめです
主要校の合格体験記や、受講生からの評判なども参考にしながら、自分に合った予備校を選ぶことが効果的です。
各予備校の特色あるカリキュラムと合格率の相関―成績向上のための講座別アプローチを詳述
合格率向上を目指すには、特色の異なる講座選びが鍵となります。予備校ごとにカリキュラムやサポート内容が異なり、それが合格実績の差にも表れています。
- 伊藤塾 ・基礎知識重視から実践演習への段階的学習
・定期的な模擬試験と個別添削指導
・合格者コミュニティによる継続サポート - TAC ・入門生・経験者を選ばず対応
・担任制や質問回答制度で疑問を個別解決
・直前期の集中講義で得点力強化 - アガルート ・映像講義専門で自宅学習最適化
・定期面談や質問対応が受講生に高評価
・合格者への全額返金制度あり - スタディング ・スマートフォン中心の効率学習
・AIを活用した弱点分析や問題演習
・短期間集中型カリキュラム
講座選びのポイント
- 学習ペースに合ったサポートが充実しているか
- 自習型か、対面・オンラインサポート重視か
- 合格率や卒業生の声を比較して最良の選択を
通信講座や独学対策のメリット・デメリット―学び方の違いが合格率に与える影響
学習方法の選択は合格率に直接影響します。行政書士試験の受験生は、通信講座や独学も多数ですが、その特徴と注意点を整理します。
通信講座のメリット
- 時間や場所に制限されず学習できる
- 映像講義やオンデマンド教材で反復学習しやすい
- 質問対応・添削サポートが充実している講座も多い
通信講座のデメリット
- 自律した学習管理が苦手な人はペースが乱れやすい
- 対面型に比べて疑問解消までタイムラグがある場合もある
独学のメリット
- 費用を安く抑えられる
- 自分のペースに完全対応できる
独学のデメリット
- 合格率は一般的に低めで、特に基礎知識がない場合は難しい
- 過去問分析や最新傾向の把握が自己責任
チェックポイント
- 合格率を高めたい場合は講座や予備校利用のほうが有利
- 独学でも法学部レベルの知識や効率的な勉強法の工夫で合格を目指すことは可能
学び方の違いを正しく理解し、自身に最適な選択肢で行政書士合格を目指しましょう。
行政書士合格率を目指すための勉強時間・学習計画と成功事例
合格者に聞く効果的な勉強時間と勉強法の実態―合格者が実践した学習計画や生活管理のポイント
行政書士試験の合格者は、確実な学習計画と生活管理で成功を収めています。多くの受験生が半年~1年の学習期間を設定し、1日2~3時間を目安に継続した勉強を行ったという結果が目立ちます。特に社会人は自己管理が鍵となり、出勤前や通勤中、夜のスキマ時間を活用するケースが多いです。
以下は合格者たちが実際に重視したポイントです。
- 学習計画を明確化し、毎週の達成目標を設定
- 基礎テキストを繰り返し確認し、過去問演習でアウトプットを重視
- 苦手分野は重点的に復習し、スキマ時間には単語カードや音声教材を活用
- 学習スケジュールはスマートフォンアプリや手帳で管理
- 勉強記録をつけて自己分析・進捗管理
学習時間の質を高めるため、暗記の工夫や定期的な模試の振り返りを重視する声も多く、効率的な勉強法が合格率向上につながっています。
一発合格率・平均受験回数と勉強時間の相関―短期合格者と長期受験者の違いを数値で解析
行政書士試験における一発合格率は約2割と言われています。一方、合格に要した平均受験回数は2~3回程度となっており、勉強時間との関連が大きいです。
短期合格者(1回合格)の特徴は、総学習時間が500時間~800時間である点です。毎日安定して学習し、弱点の把握と修正を繰り返した点が共通しています。対して、合格に複数年かかった受験者は、学習に波があり、計画性や復習の徹底度に差があった傾向が見られます。
| 受験タイプ | 平均学習時間(総計) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 短期合格者 | 500~800時間 | 毎日2~3時間、計画的学習、定期的アウトプット |
| 長期受験者 | 800時間以上 | 学習ペースに波、復習不足、基礎徹底がやや不十分 |
全体として効率的かつ計画的な学習が行政書士試験の合格率向上につながることが明確です。
試験直前対策のポイントと模試の役割―合格者が直前期に行った工夫、模試の活用法
試験直前期は、知識の総復習とアウトプット力の仕上げが重要です。合格者の多くが直前2か月で過去問と予想問題を徹底的に演習し、時間配分や問題の優先順位付けに注力しました。
- 本試験と同じ時間で模試を解き、リズムを体得
- 間違えた問題や苦手分野は特に重点的に再確認
- 新しい参考書や教材には手を出さず、使い慣れたテキストを反復
- 模試の結果をもとに弱点分析し、優先度の高い分野から対策を実施
- 試験会場のシミュレーションも取り入れる
模擬試験は自分の弱点をあぶり出し、合格基準までの距離を数値で把握できるため、合格率アップのための定番手法です。直前期の工夫と模試の積極活用が、合格という結果を後押ししています。
行政書士合格率をクリアした後の登録とキャリア形成の全体像
登録手続き・研修・登録完了までの具体的ステップ―合格後に必要な一連の流れとポイント
行政書士試験に合格した後は、すぐに実務を始めることはできません。まず行政書士会への登録手続きが必要です。登録には合格証明書、身分証明書、住民票、誓約書などの書類を準備し、居住地を管轄する都道府県の行政書士会で手続きを行います。登録申請には費用がかかり、目安として登録料や会費などを合わせて10~20万円程度が必要です。
登録後は「行政書士登録証」が交付され、必要に応じて実務研修を受講します。多くの行政書士会が実務に即した研修を実施しており、経験の少ない合格者も安心して新たな業務に臨めます。
登録までの主な流れは以下です。
- 必要書類の準備・提出
- 登録申請・審査
- 登録料・会費等の納付
- 実務研修の受講(任意・必須の場合あり)
- 行政書士登録証の受領
書類不備や手続きの遅れを防ぐためにも、事前準備が重要です。
合格後のキャリアパス・年収・求人動向の最新データ―仕事・収入面の事実と今後の展望
行政書士試験を突破した後の進路は多様です。近年は行政書士として独立開業はもちろん、企業の法務部門や事務職など事務系求人にも活躍の場が広がっています。特に法律知識や資格を生かした「転職」も注目されています。
年収に関しては、独立開業した場合、業務内容や営業活動によって差が大きく、初年度は300万円前後が多いものの、高収入を得ているケースも増えています。法人勤務の場合は、実務経験や役職によって年収水準が異なりますが、求人例としては400万円前後からスタートすることが一般的です。
最新の求人動向として「行政書士資格所有者優遇」の採用を行う企業が増えており、将来性は高い水準を維持しています。行政書士の幅広い業務知識は、企業法務や管理部門など、他職種との親和性も評価されています。
法人勤務、独立開業、求人例の比較と将来性―様々なキャリアごとの具体的な違い
行政書士のキャリア選択は、大きく分けて法人勤務、独立開業、その中間的なパターンがあります。下記のテーブルで主な違いを整理します。
| キャリアパス | 主な仕事内容 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 法人勤務 | 法務・契約書作成、許認可申請 | 400~600万円 | 安定した給与、福利厚生あり、企業サポート役 |
| 独立開業 | 役所申請代理、相談業務、書類作成 | 300~1,000万円以上 | 収入差大・集客次第、大きな裁量と自由が魅力 |
| セミ独立・副業 | 本業+行政書士業務 | 100万円~ | 副収入として活用、キャリアの幅が広がる |
行政書士資格はAI導入やDX推進の中でも依然として需要が保たれており、将来性が高い資格といえます。多様な働き方を実現できる点で、受験者の志向やライフプランに柔軟に対応できる職業です。各分野の求人例も豊富で、法律相談や行政手続き業務へのニーズが強まっています。
行政書士合格率データを活用した戦略的受験対策
過去問分析から見る合格率向上の具体的戦略―過去問活用法、合格率アップの方法論
過去の行政書士試験における合格率推移には明確な傾向があり、昭和から令和にかけて10%前後で推移しています。直近5年では12〜14%で推移し、特定の年度で合格率が上昇または低下することも確認されています。合格率に影響を与える主な要因は出題範囲の広さと法改正対応力です。
過去問活用法としては、下記の方法がおすすめです。
- 頻出テーマを把握し、優先的に対策する
- 出題傾向の変化を把握し、法改正に対応する
- 解答時間を意識して本番形式で解く
- ミス問題の解説と復習を徹底する
過去問の反復演習を通じて、知識の定着と得点力アップが図れます。合格率が安定しているため、計画的な対策を講じることで十分合格は可能です。
令和6年度の試験動向を考慮した合格プラン―最新情報に基づく計画的アプローチ
令和6年度の行政書士試験の合格率は12.9%と発表されています。受験者数の推移としては例年4万人前後で推移し、合格者数は約5,000人前後です。合格基準は総得点300点中180点以上、かつ各科目で基準点を下回らないことが求められています。
最新の傾向として、法令科目・一般知識ともに応用力重視の出題が増加しており、暗記だけでなく実践的な運用知識が問われます。特に行政手続法、行政不服審査法や民法改正など、時事的テーマが頻出しています。
行政書士合格率を高めるためには、下記の戦略が重要です。
- 法改正分野での得点源確保
- 模試や予備校講座で最新傾向に対応
- 苦手分野の早期克服
合格後のキャリアや年収、求人状況も最新データで把握しておくことが大切です。
最新合格率から導き出す受験戦略のポイント―合格率の現実から立案する有効な戦略
行政書士試験の合格率推移を下記の表で確認できます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 41,681 | 4,470 | 10.7% |
| 令和3年 | 47,870 | 5,353 | 11.2% |
| 令和4年 | 47,850 | 5,802 | 12.1% |
| 令和5年 | 47,870 | 6,124 | 13.9% |
| 令和6年 | 45,500 | 5,868 | 12.9% |
この合格率の現実を踏まえた有効な受験戦略は以下の通りです。
- 合格率が10~14%であることを理解し、着実な得点戦略を立案する
- 予備校や通信講座など信頼できる教材を活用して効率的に対策
- 学習スケジュールを明確にし、模試で実力を測定して調整する
行政書士試験は「誰でも受かる」ほど簡単ではありませんが、合格率が低い理由は十分な準備不足や基礎定着の甘さに起因します。行政書士資格取得後は公共事業や企業法務での業務拡大が期待でき、将来性や年収アップも見込めます。戦略的な準備によって合格を勝ち取りましょう。