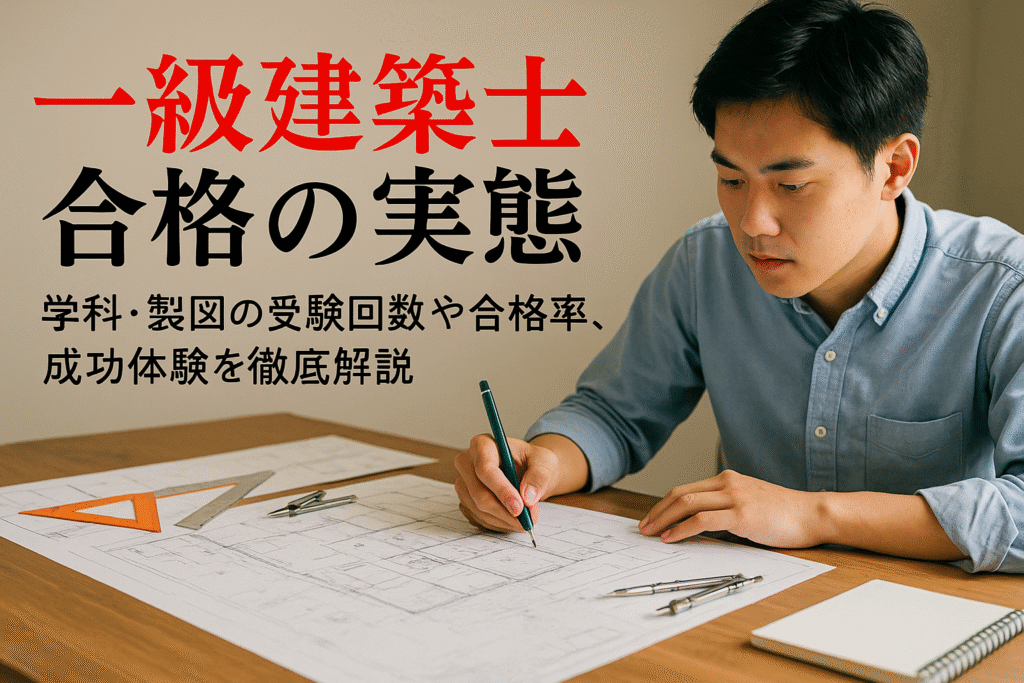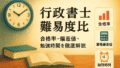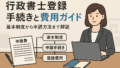一級建築士試験は、「一度きりで合格できるのか?」「何度も挑戦しなければならないのか?」と不安を抱えていませんか。
実際、直近数年の【学科試験の合格率は約13%前後】、【製図試験は約40%前後】と、どちらも狭き門です。また、合格までの平均受験回数は【2~3回】が最も多く、初回で突破する人は一部に限られています。中には5回以上挑戦して合格を勝ち取った方も少なくありません。
「なぜ一発合格が難しいのか」、どんな人が平均より早く合格できているのか、勉強継続がカギとなる実態も明らかになってきました。
さらに、経験者の体験談からは「勉強時間の確保」「問題傾向の的確な把握」「失敗からのリカバリー力」が合格への分かれ道であることが分かります。
「もう何度も落ちて心が折れそう…」そんなあなたも、正しいデータと実例を知れば、最短ルートで合格を目指せます。
初めて受験する方も、再チャレンジを考える方も、実際の合格率・受験回数・勉強法のコツをおさえて、納得感を持って一歩踏み出しましょう。
※本文では最新の統計や成功者の事例をもとに、あなたの合格可能性を高める実践的な情報を詳しく解説します。
一級建築士は何回目で合格できるのか?統計データと実体験を用いた徹底分析
学科試験や製図試験ごとの合格率推移と回数別傾向 – 合格率や受験回数の実態と推移を分析
一級建築士の合格率は、学科試験は例年およそ17〜19%で推移し、製図試験は36〜40%程度が基本です。しかし、受験者全体からみると合格率は約10%前後と非常に厳しい現状が続いています。特に学科試験に合格した年を含めて3年間、製図試験のみ再チャレンジ可能な制度があるため複数回受験する人は多く、ストレート合格(1回で学科・製図両方の合格)は約7%以下と低い数値になっています。
| 試験種別 | 合格率(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 学科試験 | 17〜19% | 例年やや高めで推移 |
| 製図試験 | 36〜40% | 学科通過者対象・対策がカギ |
| 全体最終合格率 | 約10% | 厳しい難易度・複数年受験が一般的 |
| ストレート合格 | 7%以下 | 学習経験・実力・運が大きく影響 |
こうした傾向からも、決して一発合格が当たり前の資格ではなく、数年単位で挑戦を続けるケースが大半です。
合格者の平均受験回数および成功パターンの実態 – 合格までの典型パターンと勉強継続のポイント
多くの受験生が「何年かかるのか」に関心を持ちますが、最新データと合格者の声からみても、平均2〜3回目での合格が最も多い結果となっています。建築分野の国家資格の中でも難易度が非常に高く、独学では苦戦する人も少なくありません。
-
2回目で合格:1年目で学科不合格→反省し翌年学科と製図で合格する人が多数を占めます。
-
3回目以上で合格:製図試験に複数年挑戦する方や、学科・製図とも毎年スケジュール調整に苦労する方もいます。
-
1回目ストレート合格:大学などで対策講座や演習経験がある人や、勉強時間に余裕がある人が多いです。
平均的な勉強時間は1,000時間以上が必要とされ、「毎朝2時間+週末に集中学習」など長期的なスケジュール管理が成功の決め手です。
体験談から学ぶ「何回目で合格」した理由と改善策 – 成功例や失敗例の共有と再現できる工夫
実際に複数回受験して合格した人たちは、年ごとの成果や課題を適切に分析し、アプローチを変えています。例えば「1年目で学科は合格したが製図は不合格」というケースでは、次年度に向けて製図対策の特訓や講座受講を増やすなどの工夫をしています。
-
苦手科目の明確化と重点対策:不得意分野は早期に洗い出し、重点的に問題演習を行うことで着実な学力向上を目指します。
-
模試や講座の活用:独学では限界を感じたタイミングで講師や専門スクールを利用し、効率的に合格力を養っています。
-
メンタル維持の工夫:仕事やプライベートと両立した学習スケジュール管理や成功体験のイメージ化が、長い受験生活の支えになっています。
下記チェックリストを参考に対策のポイントを確認しておきましょう。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 苦手分野の早期把握 | 毎月の自己採点で苦手科目を明確化 |
| 学習時間の見直し | 計画通りの学習消化ができているか随時確認 |
| 受験制度・免除ルールの正確な理解 | 学科合格後の製図受験期間や再チャレンジ条件等 |
| モチベーション維持の工夫 | 仲間やSNSなどで切磋琢磨できる環境づくり |
複数年かけてでも諦めず、計画的に勉強と生活を両立させる姿勢が合格への最短ルートとなります。
一級建築士試験の高難易度と低合格率のリアルな背景
低合格率が続く根本的要因の分析 – 試験制度や範囲、採点基準の特色と課題を深堀り
一級建築士試験は毎年多くの受験生が挑戦する国家資格ですが、合格率は約10%前後にとどまっています。主な理由として、試験範囲の広さが挙げられます。学科は建築計画、法規、構造、施工など専門性が高く、さらに製図試験では図面作成だけでなく設計意図や法規解釈まで問われます。採点基準も厳格で、細かなミスや法令違反が即不合格の判定材料になることも頻繁です。加えて、暗記や知識だけでなく、応用力や判断力が総合的に求められるため、短期間の学習で合格するのは非常に困難です。範囲と難度のダブルパンチが長年にわたり低合格率を維持する要因です。
他国家資格および二級建築士との合格率・難易度比較 – 他資格との比較で難易度を客観視
さまざまな国家資格の中で一級建築士の難易度は特に高いとされています。以下のテーブルで、代表的な資格との合格率を比較します。
| 資格 | 合格率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一級建築士 | 約10% | 学科・製図の両方合格が必要 |
| 二級建築士 | 約20〜25% | 出題範囲が一級より狭い |
| 行政書士 | 約10〜13% | 法律知識が主に問われる |
| 宅地建物取引士 | 約15〜17% | 法令と不動産実務が中心 |
一級建築士は二級建築士よりもはるかに難しく、専門学校や大学での学習経験がなければ独学では対策が難しい資格といえます。また、試験範囲の膨大さやハイレベルな製図試験が他資格との大きな違いです。
受験生属性と学歴・実務経験の関連性 – 受験生の傾向と合格率への影響を分析
一級建築士の受験者は、建築学科出身や建築系専門学校卒業者、さらにゼネコン・設計事務所など実務経験者が中心です。学歴や職務経験が合格率に大きく影響しています。たとえば大学の建築学科卒は基礎知識が充実しているため、初回・2回目での合格ケースが多い傾向にあります。一方、他学部から参入する場合や実務経験が浅い場合は、知識や図面の実技経験が不足し、複数回の受験を経て合格するケースが一般的です。
受験生データの特徴を下記にまとめます。
-
建築学科卒の合格率が高い
-
三大都市圏在住・大手ゼネコン勤務者は勉強環境が良く、合格が早い傾向
-
実務経験が豊富な人は製図で有利
-
年齢層は20代後半〜30代が最多だが、40代以上の合格者も少なくない
これらの属性をもとに、自分に合った対策を立てることが合格への近道です。関心を持つ再検索ワードや悩みは多いですが、経験や学歴を冷静に自己分析し、最適な勉強計画を立てることが成功のカギとなります。
合格までに必要な勉強時間と年数の目安、効率的な学習計画の立て方
勉強開始時期から合格までの平均的スパン – 勉強スタートから合格までにかかる現実的な期間
一級建築士試験の合格には1,000〜1,500時間以上の勉強が必要とされ、平均的な合格までの期間は2〜3年が目安です。一発合格(ストレート合格)率はおよそ7%に留まり、ほとんどの受験者が2回目、もしくは3回目以降で合格を果たしています。学科試験と製図試験を連続で突破できる可能性は高くないため、学科で1年、翌年以降に製図合格というパターンも多いです。長期化を避けるためには、無理のない計画性と粘り強い継続が重要です。
下記は勉強開始時期から合格までの一般的な流れとその特徴です。
| 勉強年数 | 主な合格層 | 勉強方法や特徴 |
|---|---|---|
| 1年目 | 建築学科卒、実務経験豊富な方 | 集中型学習、1日3〜4時間 |
| 2〜3年目 | 働きながら学ぶ社会人、子育て受験者 | 計画型・反復練習重視 |
| 4年目以降 | 多忙・再受験者、独学・自力突破型打者 | 弱点分析、個別対策 |
特に仕事や家庭と両立しながらの場合、1年での合格はまれですが、正しい戦略と生活バランスが合格への近道となります。
合格率を上げる重点学習方法と効率的ルーティン – 合格者が実践した効率的な学習モデル例
合格者が実践している効率的な学習方法には下記のような特徴があります。まず全体像を把握し、科目別に重要ポイントを絞ることが成功の秘訣です。
-
過去問分析の徹底
- 過去10年分の問題に繰り返し取り組む
- 出題傾向と頻出テーマを抽出し、重点化
-
弱点分野の早期洗い出し
- 模試や自己採点で苦手分野を特定
- 毎週小テストで確認し改善
-
製図の戦略的対策
- 時間配分練習を重視
- エスキスや作図の反復で本番力を養成
-
継続できる学習リズム作り
- 1日2〜4時間、週5日以上を目安にコツコツ継続
- 生活ルーティンの中に学習時間を組み込む
| 学習項目 | 重点ポイント | 効果を高めるコツ |
|---|---|---|
| 学科対策 | 頻出分野・過去問中心 | 毎日短時間でも継続 |
| 製図対策 | 時間配分、作図手順の最適化 | 本番同様の模試練習を反復 |
| 模試・総復習 | 実戦形式でペース配分を訓練 | 評価→見直し→改善サイクル強化 |
ストレート合格を目指す場合は早期から全体像の把握と計画的な学習が不可欠です。独学の場合でも、市販テキスト、オンライン講座、模試を賢く活用し合格者の成功モデルを自分なりに取り入れることが効果的です。効率よく進めるためには、目標(学科突破→製図合格)を明確に、学習記録を残すことが意欲と成果の持続に繋がります。
合格者の特徴・性質と続けられる心構え―成功者の共通点
合格しやすい人の資質と心構え – 不合格者との比較や継続できる思考習慣の分析
一級建築士試験で合格を勝ち取る人には共通する特徴があります。それは学習習慣の徹底と自己管理能力の高さです。初学者であれば必要な勉強時間は1000時間を超えることも多く、長期間にわたる安定した努力が不可欠です。
特に合格しやすい人は、次のような資質・心構えが見られます。
-
強い目的意識とモチベーションを持っており、途中で諦めない
-
失敗や課題に直面しても自分の弱点を冷静に分析し、計画を修正できる
-
周囲と比較せず、自分のペースを守って継続できる
-
具体的な勉強スケジュールを作り、効率的に知識を蓄える
これに対し不合格を繰り返す人は、自己分析や対策の修正ができていない場合が多く、学習法に固執しがちです。合格した人の多くは過去問研究や反復学習、建築関係の最新知識のインプットを重視しています。
資格の価値や取得後の年収アップも視野に入れ、継続的な努力と前向きなマインドを保つことが、一発合格だけでなく2回目以降で成功を掴む共通点と言えます。
失敗しやすいパターンと回避のための方法論 – つまずきやすいポイントと克服策を具体的に
一級建築士試験で失敗する主な理由としては、以下が挙げられます。
-
計画的でない学習(準備不足ややみくもな勉強)
-
学科・製図の片方だけに偏った学習
-
忙しさやストレスで進捗管理ができなくなる
-
問題を解いた数だけに満足し、理解が浅いまま進む
合格への近道として、つまずきを克服するための実践的な方法を紹介します。
-
学科と製図の両立を意識して、バランス良く学習内容を割り振る
-
スケジュール管理アプリやカレンダーで進捗状況を見える化する
-
苦手分野の洗い出しを行い、反復学習で知識の定着度を高める
-
模試や過去問を積極的に活用し、自分の理解度を定期的に確認する
以下のテーブルで、よく見られる失敗パターンと推奨される改善策を整理します。
| 失敗しやすいパターン | おすすめ改善策 |
|---|---|
| 遅れがちな進捗管理 | 週単位で目標設定し振り返り |
| 製図で失点しやすい | エスキス練習の反復と添削活用 |
| 独学で孤立する | 講座や学習コミュニティ活用 |
| 勉強時間の確保不足 | 毎日決まった時間を勉強に充てる |
試験の難しさや合格のすごさに戸惑う声も多いですが、しっかりとした準備とメンタルの維持が突破のポイントです。計画→実行→分析→修正のサイクルを回し、合格への歩みを止めない姿勢が大切です。
一級建築士の価値と取得後のキャリアアップ・年収相場
資格取得後の平均年収と実務活用事例 – 年収の目安・職種別の具体事例を紹介
一級建築士は建築業界で最上位クラスの資格であり、取得後の年収やキャリアパスは大きく広がります。年収の目安としては、一般的に500万円〜900万円程度が多く、設計事務所やゼネコン・デベロッパー・公務員など働く環境によって幅があります。
以下は職種や勤務先別の年収目安をまとめたテーブルです。
| 職種・業態 | 平均年収 | 特徴 |
|---|---|---|
| 設計事務所(一般社員) | 500万~650万円 | 実力重視。若手〜中堅で昇給、大手ほど高水準 |
| ゼネコン(現場・設計部門) | 600万~900万円 | 一級取得で役職・年収アップ。プロジェクト規模に関わる |
| 独立開業(自営含む) | 400万~1500万円 | 受注数・実績力で収入差大。上位層は年収1000万円超も |
| 公務員(技術職・建築部門) | 500万~700万円 | 年功序列が基本。資格手当・昇進に有利 |
| デベロッパー勤務 | 700万~1000万円 | プロジェクト全体管理、好条件。大手企業が高年収傾向 |
一級建築士を取得することで、設計分野のみでなく、施工管理や都市開発、企画・商品開発まで仕事の幅が広がります。二級建築士や未資格者とは、携われる業務領域や責任範囲が大きく異なり、プロジェクトのリーダーや管理者として活躍できる場面が増加します。
社会的価値と職場での評価の変化 – 社会的信頼や周囲の反応・評価の推移を詳しく解説
一級建築士の社会的価値は極めて高く、建築界のみならず社会全体で強い信頼を得られる資格です。職場では、一級建築士を取得したことで現場責任者への登用や大規模プロジェクトを任されることが増えるなど、キャリア上の飛躍が実感できます。
取得時の周囲の反応としては、上司や同僚、取引先からの信頼度・評価が飛躍的に向上し、名刺や公式資料でも「一級建築士」の肩書きが強調されます。転職市場でも高評価となり、好条件のオファーや昇進・昇給のチャンスが増えます。
-
社会的な変化・メリットのリスト
- 大規模設計や公共工事など、より責任ある仕事・案件への参加が可能になる
- 取引先や顧客からの信用度アップ
- 資格手当や昇進要件への該当で、年収や役職も上がりやすい
- 二級建築士や未取得者との明確なキャリア格差の発生
- 知恵袋や体験談でも誇りを持って語られる場面が多い
一級建築士の取得は「人生が変わる」と評されることも多く、専門職の中でも特に社会的地位や評価、将来性が約束された存在とされています。
受験資格・制度の最新情報と大学・専門学校別合格状況の比較
免許登録時の実務経験ルール変更の詳細 – 制度変更による受験影響と注意点を具体的に解説
一級建築士試験の受験資格は、大学や専門学校で所定のカリキュラムを修了することに加え、以前は免許登録時に一定の実務経験が必要とされていました。近年の制度変更により、学科・製図の両試験合格後でも、すぐに免許登録できるような仕組みへ移行しています。これにより、卒業からキャリア設計を立てやすくなり、受験可能なタイミングが広がりました。
特に注意すべき点として、実務経験の証明方法が具体的になり、申請書類の不備によるトラブルも増加しています。最新制度では、勤務先の証明や職務内容の記載が厳格化されているため、各自が早めに用意しておくことが合格後の登録手続きを円滑に進めるポイントとなります。こうした変更は、学生や社会人受験者の双方にメリットを生み出しています。
大学・専門学校別の合格率傾向とその要因分析 – 学歴ごとの合格率・傾向を詳細に解説
一級建築士試験では、大学や専門学校ごとに合格率に大きな差が認められます。大手大学卒はカリキュラムが充実しており、学科試験・製図試験とも高い合格率を維持しています。一方、専門学校や独学でチャレンジする受験生も多く、それぞれの学習環境によって結果が分かれています。
下記は最新の合格率傾向です。
| 区分 | 学科合格率 | 製図合格率 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 大学卒 | 22% | 38% | 体系的な知識習得が強み |
| 専門学校卒 | 17% | 32% | 実務経験を早く積める |
| 独学・他 | 9% | 24% | 情報不足・学習管理が課題 |
要因分析のポイント
-
大学では学内講座や模擬試験の支援が充実し、過去問対策も万全。
-
専門学校は実践型授業が多く、早期に現場感覚が磨かれる。
-
独学はモチベーション維持と最新情報のキャッチアップが合否の分かれ道となります。
独学者の現状と資料活用法 – 独学派の成功事例と学習サポート法
独学で合格した受験者は全体の約1割程度にとどまりますが、近年はオンライン講座や参考書、SNSでの情報交換を駆使した成功事例が増えています。独学最大の壁は「学習範囲の把握」と「計画的な進行」です。
成功する独学者の特徴
-
過去問を徹底的に分析し、出題傾向に即した勉強スケジュールを組む
-
オンライン模試や専門学校の通信教材を有効活用
-
ノートやエスキス集、作図練習などアウトプット型学習を主体に進めている
おすすめサポート法
-
公式サイト・資料の活用:国土交通省や建築士試験センターの最新情報をこまめに確認
-
学びのコミュニティ:SNSグループや勉強会に参加し、情報交換・モチベーション持続を図る
-
時間管理アプリの利用:毎日の進捗記録を習慣化し、継続的な学習を支える
独学での突破は決して夢ではありませんが、資料やサポートツールの活用は必須です。自分にあったリソースを見つけ、計画的に学習を進めることが合格への最短ルートになります。
試験科目別:学科対策・設計製図突破のための具体的勉強法と落とし穴
学科試験の科目別対策法と記述ポイント – 科目別難所と得点アップのコツを提示
一級建築士の学科試験は、建築計画・環境、法規、構造、施工、建築史の5科目で構成されます。各科目で出題傾向と難易度が異なるため、計画的な学習が必要です。特に法規は膨大な条文の理解とスピードが得点の鍵を握ります。構造は計算問題が多く、例題演習と基礎公式の確実な暗記がおすすめです。施工は過去問題集を使って、頻出箇所を繰り返し確認すると効果的です。分野ごとに苦手をそのままにせず、弱点科目は重点的に繰り返し学習するのが合格への近道です。
<科目別 難所と学習ポイント一覧>
| 科目 | 難所 | 得点アップのコツ |
|---|---|---|
| 法規 | 時間内回答・複雑な条文 | 六法の速読み&模擬試験繰り返し |
| 構造 | 構造力学・計算 | 例題反復・基礎公式の完全暗記 |
| 施工 | 工法・建材・工程 | 過去問重点学習・具体例で覚える |
| 計画・環境 | 空間設計全般・環境制御 | 苦手分野の重点確認・直近出題の徹底把握 |
| 建築史 | 語句・年号 | 用語カード・イラスト学習で記憶定着 |
製図試験のエスキス・作図の実践技術と時間配分 – 製図作業の手順やタイムマネジメント解説
製図試験ではエスキス(設計の下書き)と正確な作図が要求されます。多くの受験者が「受かる気がしない」と感じるのは、制限時間内に全工程を終える難しさにあります。最初の60分で敷地条件やゾーニング、動線設計の方針をしっかり定めましょう。その後はエスキス図を元に各作図へ移行し、時間配分表を事前に作成して訓練するのが効果的です。清書の際に焦りや書き直しで手戻らないためにも、エスキスの段階でミスを潰す能力が合格には不可欠です。練習時から時間を意識し、20分ごとの見直し習慣をつけることで、安定した完成を目指せます。
<製図試験 時間配分モデル>
| 工程 | 推奨時間 |
|---|---|
| エスキス | 60分 |
| 作図 | 150分 |
| 記述 | 30分 |
| 見直し | 30分 |
| 合計 | 270分 |
成績アップのための効果的教材と講義活用例 – おすすめ教材や効率的な講義活用術
短期間合格や2回目での合格を目指す場合は教材・講義の取捨選択が重要です。代表的な独学向け教材としては過去問題集、分野別の解説書、要点整理ノートが挙げられます。オンライン講座や対策学校も有効ですが、疑問点を即座に解決できる個別指導型や質問受付体制の整ったものを選ぶことで信頼性が高まります。定評のある大手資格学校の模擬試験や講義を活用すれば「なぜ合格率が低いか」「合否を分けるポイント」も明確に分析できます。テキストと動画講義の併用で内容理解を深め、定期的な自己分析で弱点を克服してください。
<おすすめ教材・講座の特徴比較>
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 過去問題集 | 出題傾向把握・弱点対策に最適 |
| 要点整理ノート | 時間のない社会人・独学者の効率学習向け |
| オンライン講座 | 時間と場所を問わず反復視聴が可能 |
| 模擬試験 | 実力診断・本番対応力向上に有効 |
| 個別指導 | 苦手分野の攻略・細かな疑問解消 |
このように計画的な対策と適切な教材選び、実践的な学習方法の組み合わせが、難関と言われる一級建築士試験合格に直結します。
一級建築士試験にまつわるよくある質問と疑問解消コーナー
合格までの受験回数の制限とは? – 受験回数に関する制度やルールを具体的にまとめる
一級建築士試験には受験回数の制限は設けられていません。年齢や学歴、実務経験などの受験資格を満たしていれば、何度でも挑戦できます。多くの受験者が2回目、3回目で合格していますが、5回以上かかる例も珍しくありません。近年では、ストレート合格率が7%ほどとされており、一度で合格できる可能性は低いのが現実です。受験への挑戦をあきらめることなく、計画的に取り組むことが重要となります。特に、初回は学科・製図共に受験する形となるため、長期的な学習スケジュールを立てましょう。
学科合格後、製図試験は何回まで受けられる? – 製図試験再受験の仕組みや注意点
学科試験に合格すると、その合格は3年間有効です。つまり、1度学科に合格すれば、残り2回まで製図試験に進むことが可能です。この仕組みにより、学科に合格後、万一初回の製図で不合格になった場合でも、翌年・翌々年は学科を受けずに製図のみ再受験できます。一方、有効期間が過ぎると学科の再受験が必要になるため、できる限り早く製図試験まで合格を目指すことがポイントです。製図は難易度が高く、「製図受かる気がしない」と感じる人も多いですが、続けての挑戦に希望が持てます。
合格率が年々変動する要因は? – 合格率変動の背景や試験環境の変化を解説
一級建築士の合格率は年度ごとに変動しており、背景には試験内容や出題傾向、受験者の学力レベルの変化が影響しています。例えば、問題の難易度が高くなる年や新しい傾向が導入される年は、合格率が下がることがあります。また、合格基準点が例年より高かった場合にも合格者数は減少します。さらに資格学校での情報共有や学習方法の進化によって、合格者全体の傾向が変化することも。試験対策としては、過去問だけに頼らず、最新の傾向を意識した学習が重要です。
独学・予備校それぞれの効果と選び方は? – 効果的な選択肢とメリット・デメリットを比較
一級建築士試験対策には独学と予備校の2つの主な方法があります。独学は自己管理力が問われますが、費用を抑えられる点がメリットです。一方、予備校は体系的なカリキュラムや添削指導が得られ、合格までの道筋をより明確にできます。下表で特徴を比較します。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 独学 | 費用が安い、スケジュールが自由 | 情報不足、モチベ維持が難しい |
| 予備校 | 指導が体系的、疑問をすぐ解消できる | 費用が高い、通学負担がある |
自分の学力や生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。経験者の声では、予備校利用者の合格率が高い傾向にありますが、独学でも毎年合格者は出ています。
一級建築士資格で実生活やキャリアはどう変わる? – 資格取得による転機や実体験を具体的にまとめる
一級建築士資格を取得すると人生が変わると表現されるほど、仕事や生活に大きなインパクトがあります。就職・転職市場での評価が高まり、年収アップを目指せる点が魅力です。一級建築士 年収は企業規模や役職により差がありますが、経験や実力が伴えば高年収も夢ではありません。また、社会的信用や自信が生まれ、責任ある仕事を任される機会が増えます。資格取得の努力や知識が認められ、家族や周囲からの信頼も向上することが多いです。自分の設計が社会に形として残る経験は、他にはない大きなやりがいとなるでしょう。