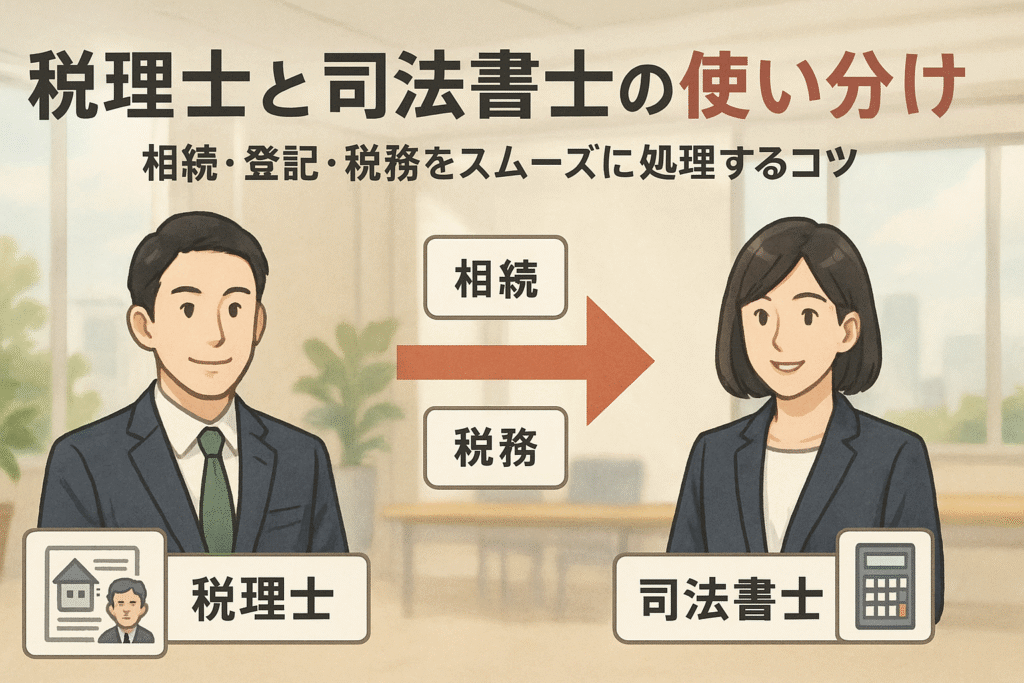「相続登記は司法書士?それとも税理士?」――期限や窓口が違うため、最初の一歩でつまずきやすいテーマです。例えば相続税は原則10か月以内、相続登記は2024年から原則義務化。会社設立でも、定款認証・登記と開業届・税務手続で担当が分かれます。迷いを減らし、ムダな往復や追加費用を避けたい方へ。
本記事では、税務申告・相談に強い税理士と、不動産・商業登記に精通する司法書士の役割と独占業務をやさしく整理。相続や設立での「優先順位」「準備リスト」「連携フロー」をケース別に解説します。境界領域で起きやすい依頼ミスのチェックポイントや、費用が上下する要因、見積りで確認すべき条件も具体的に示します。
相続財産が不動産中心か金融資産中心か、事業承継が絡むかで最適ルートは変わります。はじめに何を集め、誰に何を頼むか――実務に直結する手順で、今日から迷わず進められるようにご案内します。
税理士と司法書士の違いをまず理解!役割と独占業務をやさしく整理してみよう
税理士の業務はどんなことまで?税務代理や申告・相談の実態を知る
税理士は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つが独占業務です。個人の確定申告や法人の決算申告、相続税の申告、消費税や法人税の計算と提出、税務調査対応まで幅広く関与します。記帳代行や会計ソフト導入支援、資金繰りや経営のアドバイスなども担い、申告の精度と期限管理を徹底してくれるのが強みです。相続では、遺産の評価や特例の適用判断を行い、申告から納税方法の相談まで一気通貫でサポートします。一方で、登記や法務書類の提出は司法書士の領域であり、税理士は直接扱いません。税務と会計の実務に強いので、数値の見える化と節税余地の発見に価値が生まれます。税理士 司法書士の比較では、税理士は税務・会計に軸足があり、手続の相手が税務署である点が特徴です。
-
相続税や法人税、消費税など税目横断で対応
-
税務調査や申告期限の管理に強い
-
会計・経営の継続支援で企業の成長を後押し
税務代理と書類作成のボーダーラインは?実務で気をつけたいポイント
税務の現場では、どこまでが税務代理でどこからが単なる書類作成かを明確にしておくことが重要です。税務代理は、税務署への申告・申請・照会への回答や税務調査の立会いなど、納税者に代わって権限を行使する行為で、税理士のみが担当できます。書類作成は、申告書や届出書の作成そのものを指し、これも税理士の独占領域です。相談についても、税法の解釈や適用を伴う助言は税理士の業務になります。実務では、委任契約で代理範囲や作業内容、成功報酬の有無、追加料金の発生条件、実費(登録免許税や郵送費など)の扱いを事前に合意してください。電子申告のID管理や源泉所得税の年末調整の役割分担、会計データの受け渡し方法も明記するとトラブルを回避できます。相続では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成支援と、相続税の評価・申告を区分し、司法書士との連携範囲も合わせて可視化しておくと安心です。
司法書士の業務はどこで活躍する?登記や書類作成・各種手続に強い理由
司法書士は、不動産登記・商業登記・供託手続・裁判所提出書類の作成を中心に活躍します。不動産の所有権移転や相続登記、抵当権設定の申請、会社設立や役員変更の登記、商号変更など、登記の正確性と期限厳守が評価の要です。相続領域では、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援、名義変更や口座解約に必要な書類整備など、手続の全体設計に強みがあります。簡易裁判所での訴訟代理等認定を受けた司法書士は、一定範囲の民事紛争にも対応できます。税理士 司法書士の連携が求められる典型は、相続財産の評価と相続税申告(税理士)と相続登記(司法書士)が同時並行で走るケースです。法務と手続を正しく進めるため、原本確認・本人確認・添付書面の整合性に細心の注意を払う点がプロの価値となります。
| 業務領域 | 税理士が強い場面 | 司法書士が強い場面 |
|---|---|---|
| 相続 | 相続税の試算、評価、申告、納税方法の相談 | 相続登記、戸籍収集、名義変更、協議書作成支援 |
| 企業 | 法人税・消費税申告、節税提案、月次決算 | 会社設立登記、役員変更、定款変更登記 |
| 手続 | 税務署対応、税務調査立会い | 法務局・裁判所・供託の申請 |
登記の正確性は後戻りが難しいため、必要書類のチェックリスト化とスケジュール管理が成功の鍵です。番号手順で進めるとミスが減ります。
- 目的と期限を確定し、必要書類をリスト化する
- 戸籍や評価資料を収集し、内容を相互に確認する
- 電子申請や窓口提出の方法を選び、費用と実費を整理する
- 登記完了後、税務や名義変更の残タスクをフォローする
手続の道筋が見えると、費用と時間の見通しが立ち、安心して依頼しやすくなります。
相続で迷わない!税理士と司法書士はどう使い分ける?最強の連携術
相続登記と相続税申告、どちらを先に進めると良い?手続の優先順位と準備リスト
相続のスタートは情報の正確な把握です。相続登記は不動産の名義変更、相続税申告は相続税の計算と納付で、期限や要件が異なります。原則は期限がある相続税申告(10か月)を意識しつつ、登記の準備を同時並行が安全です。まずは戸籍収集と相続人確定、財産の洗い出し、遺産分割協議書の作成に着手します。税務は税理士が、登記は司法書士が担当し、情報共有が早いほど手続は短縮されます。特に不動産の評価や小規模宅地の特例など税額に影響する論点は早期検討が必須です。迷ったら両者へ初回相談を行い、進行表を作って抜け漏れを防ぎましょう。
-
優先の考え方
- 期限のある相続税申告を最優先で逆算
- 登記は遺産分割がまとまり次第でOK(放置は非推奨)
相続財産の内容によって違う!依頼先の選び方 不動産と金融資産のパターン別解説
財産構成に応じて依頼の主軸が変わります。不動産中心なら、名義変更や法務手続に強い司法書士を起点に、評価や税額計算で税理士が加わる流れが合理的です。預貯金や有価証券など金融資産中心なら、相続税や申告の要否判定を税理士が主導し、口座解約や名義変更の書類面は司法書士が補助しやすいです。事業承継が絡む場合は、株式評価、役員変更登記、経営資源の整理が同時進行になるため税理士と司法書士の連携が不可欠です。相続人間の合意形成が難しいケースは、早い段階で専門家が手続の道筋と必要書類を提示し、相続人の負担とトラブルの芽を減らします。費用は案件の複雑性で変動するため、見積と作業範囲の明確化が重要です。
| パターン | 主な課題 | 起点にする専門家 | 連携の要点 |
|---|---|---|---|
| 不動産中心 | 名義変更・評価 | 司法書士 | 固定資産評価と税特例を税理士が確認 |
| 金融資産中心 | 申告要否・配分 | 税理士 | 口座手続の書類を司法書士が整備 |
| 事業承継あり | 株価評価・登記 | 税理士 | 役員変更や持株移転の登記を司法書士 |
金融機関の手続きは各社ルールが細かく、書類不備で差し戻しが起きやすいため、事前のチェック体制が効きます。
手続きがスムーズに進む!税理士と司法書士の相続連携フローを一挙解説
効率的な進め方は情報の一元化と同時並行です。初回ヒアリングで相続人・相続財産の全体像を把握し、役割分担と期限を確定します。税理士は相続税の試算、評価、特例適用の可否を見極め、司法書士は相続関係説明図、戸籍収集、登記申請書の設計を進めます。遺産分割協議書は税務要件(特例の要件)と登記事項の両立を必ず確認します。進捗共有はチェックリストで可視化し、提出期限前にレビューを行うと精度が上がります。
- 初回ヒアリングと資料収集の指示
- 相続人確定(戸籍類の収集)と財産目録の作成
- 税理士による評価・試算と方針提示
- 遺産分割協議書の作成と合意
- 相続税申告と不動産の相続登記申請
手順を明確化すると相談者の負担が軽くなり、期限遅延や書類不備のリスクを大幅に低減できます。
会社設立や事業スタート時に迷わない!司法書士と税理士はどう使い分ける?
商業登記と税務届出はここが違う!定款認証から開業届までを一目で理解
会社設立の初動は、司法書士が商業登記を中心に、税理士が税務と会計の初期設計を中心に担当します。流れを時系列で分けると整理しやすく、電子申請の可否もポイントです。まず発起人決定や商号・本店・事業目的の確定、定款原案の作成を行い、定款認証は公証役場での手続が必須です。その後、出資金の払込み、登記申請(会社成⽴)は司法書士が代行可能で、オンライン申請に対応します。登記完了後に法人番号が付与され、税務署・都道府県・市区町村へ開業届や青色申告承認申請などを税理士がサポートします。社会保険や労働保険の適用手続は別途必要で、電子申請の使い分けで時間短縮が可能です。税理士と司法書士の連携で相続税や不動産登記が絡むケースにも対応しやすくなります。
| ステップ | 主担当 | 主な手続 | 電子申請可否 |
|---|---|---|---|
| 定款作成・認証 | 司法書士 | 定款原案、認証手続 | 一部対応 |
| 資本金払込み | 依頼者 | 口座入金・証明準備 | 不可 |
| 設立登記申請 | 司法書士 | 登記書類作成・申請 | 可能 |
| 税務届出 | 税理士 | 開業届・青色申告・消費税関係 | 可能 |
| 社会保険手続 | 社会保険分野の専門家 | 新規適用・資格取得 | 可能 |
節税もガバナンスも最初が大切!会計と登記を同時進行させるコツ
設立直後のつまずきは、後からの修正コストが大きくなります。資本金の額・払込方法・資本準備金の振分は節税と信用力のバランスを見て決めると良いです。役員構成は任期や職務権限を明確化し、取締役会の有無や代表権の範囲を定款と登記で一致させましょう。税務面では、会計科目の初期設定、会計ソフト選定、青色申告承認の期限管理(設立日から原則3か月以内)が重要です。さらに、消費税の適用判定やインボイス対応は資金繰りと取引先要件に直結するため、開始時点で税理士に確認すると安全です。会計と登記を同時進行させるコツは次の通りです。
- 登記前に資本金・機関設計の案を税理士と確認し、将来の増資や相続対策の余地を残す
- 定款・議事録の表現を会計処理と整合させ、役員報酬や決算期を明確にする
- 証憑収集から会計入力までの運用フローを設計し、締日と提出期限を共有する
- 銀行口座・クレジット・会計ソフトの連携で自動化を進め、入力ミスと時間を削減する
上記を整えると、司法書士の登記書類と税理士の申告・申請書類がブレず、ガバナンスと節税の両立がしやすくなります。
料金相場もこれで安心!追加料金を回避する税理士と司法書士への依頼の極意
料金の目安と費用が上下するワケ 作業量や難易度でこんなに変わる
税理士と司法書士への依頼費用は、案件の難易度や作業量、緊急性、必要書類の収集範囲で大きく変わります。相続や不動産の登記、相続税の申告のように関係者や書類が多いケースは時間がかかり、実費と報酬の両面で上振れしやすいです。例えば税務の申告は仕訳件数や年数、修正申告の有無で、司法書士の登記は物件数や名義変更の有無で費用が伸びます。以下の相場イメージを踏まえれば、見積りの妥当性を冷静に判断できます。急ぎの対応、戸籍や謄本の広範な収集、相続人の確定が難しい案件は、工程が増えるため追加の人件費や郵送費が発生しがちです。事前に作業範囲を絞り、必要な書類を可能な限り準備しておくと、費用を抑えやすくなります。
| 区分 | 典型業務 | 料金の目安 | 変動要因 |
|---|---|---|---|
| 税理士 | 確定申告・相続税申告 | 作業量と難易度で幅が大きい | 仕訳件数、年数、修正の有無、期限までの時間 |
| 税理士 | 顧問・記帳代行 | 取引規模に比例 | 取引件数、レポート頻度、訪問有無 |
| 司法書士 | 不動産登記 | 物件や名義数で増減 | 物件数、持分、評価、必要書類の取得範囲 |
| 司法書士 | 相続関連書類作成 | 相続人の数と戸籍収集量 | 相続人確定、遺産の種類、協議書作成の有無 |
短納期化の相談は早めに行い、優先度の調整で追加費用を最小化すると安心です。
見積りで損しない!契約時に必ずチェックしたい条件とリスク
契約前の見積りでは、報酬区分と実費の線引きを明確にしましょう。特に着手金、成功報酬、時間単価の上限、郵送や登録免許税などの実費の見込みが曖昧だと予算超過の原因になります。以下を確認すると追加料金を回避しやすいです。
-
作業範囲の定義(どこまでが報酬に含まれるか)
-
成果物の内容(書類作成、申請代行、相談回数)
-
中断・追加発生時の精算条件(相続人増加や資料追加時の単価)
-
納期と優先対応の可否(短納期の加算率)
-
連絡手段と頻度(修正回数の上限)
税理士に税務、司法書士に登記や法務手続の役割を明確化すると、ダブルライセンスの事務所でも費用の重複を避けられます。相続や不動産の案件では、戸籍の収集範囲や相続財産の確定方法を事前に共有し、固定額と従量課金の境目を文面で残すことが重要です。見積書と業務委任契約書の整合性を確認し、追加作業は都度合意のルールにしておくと安心です。
税理士や司法書士のどちらに相談すればいい?ケース別で選ぶ最適ルート
迷ったときの即判断!相続・不動産・会社設立のよくあるシーンで選択術
相続や不動産の名義変更、会社設立で迷ったら、まずは手続きの入口を見極めましょう。相続では、相続財産の評価や相続税の申告・節税は税理士、戸籍収集から相続人確定、遺産分割協議書の文案作成、相続登記の申請は司法書士が担当します。不動産売買では、譲渡所得の計算や申告は税理士、所有権移転登記や抵当権変更の申請は司法書士が専門です。会社設立も同様で、資本金や役員報酬の設計は税理士、定款認証の前提となる登記申請書類の作成と申請代理は司法書士がスムーズです。迷う場面ほど両方に段取り確認を。ワンストップで連携可能な事務所なら、期限管理や書類収集の手間を大幅に削減できます。
-
相談の起点を税務か登記かで仕分けすると判断が早いです
-
申告期限や相続登記の期限は先に確認して遅延リスクを回避します
-
手続きが連動する場合は連携実績のある事務所が安心です
境界領域には要注意!誤った依頼を防ぐ実務チェックポイント
税理士と司法書士の境界は、税務代理と登記申請代理に明確な線引きがあります。税務の意見表明や申告書の提出代理は税理士のみ可、登記の申請代理は司法書士のみ可です。相続では、遺産分割協議の内容が複雑なときに税額の試算だけでなく、名義変更の要件や戸籍の精査が必要になるため、早期に双方へ相談すると手戻りを防げます。次のチェックで誤発注を回避しましょう。
- 手続きの主目的は税務申告か登記申請かを一文で言語化する
- 必要書類に「申告書」か「登記申請書」が含まれるかを確認する
- 期限の有無と法定期限を先に押さえる
- 費用の内訳に「代理提出」や「登録免許税」「税額計算」が入るかを確認
- 連携が前提の案件なら窓口を一本化してスケジュールを共有する
相続、会社、不動産のどのケースでも、法律相談が必要な争訟性の高い内容は弁護士の領域です。税理士司法書士のダブルライセンス事務所なら、相続税と相続登記の同時進行がしやすく、書類の重複収集も抑えられます。
| シーン | まず相談する士業 | 主な業務範囲 | 注意すべき期限 |
|---|---|---|---|
| 相続で不動産名義変更 | 司法書士 | 相続人確定、協議書作成、相続登記申請 | 相続登記の申請期限 |
| 相続税の有無を知りたい | 税理士 | 相続財産評価、相続税試算・申告、節税助言 | 相続税申告期限 |
| 会社設立 | 司法書士 | 設立登記の書類作成・申請代理 | 設立日程の調整 |
| 決算と申告 | 税理士 | 会計、税務申告、税務相談 | 申告・納付期限 |
手続きの入口を正しく選べば、時間も費用も無駄にしません。境界領域は必ず確認し、必要に応じて両方へ相談しましょう。
ダブルライセンスって本当に有利?税理士と司法書士の資格を両方持つ魅力と現実
メリットは圧倒的な連携力と幅広い提案!依頼者の体験価値がここまで変わる
税務と法務を横断できるダブルライセンスは、相続や会社の登記と税務申告が絡む複合案件でワンストップ対応を実現します。相続財産の評価と相続税の申告、名義変更や不動産の登記申請まで一気通貫で進められるため、手続きの漏れや重複コストを削減できます。さらに、税理士が示す節税の選択肢と司法書士の法務的リスク評価を合わせれば、遺産分割協議書の設計精度が向上し、依頼者の不安が軽減します。経営者支援でも、組織再編や株式の承継スキームなど、税務と登記のタイムラインを揃えて提案できる点が強みです。求人や転職情報の市場でも、連携のハブとなる実務力は評価されやすく、事務の効率化や顧客満足にも直結します。
-
対応範囲の拡大により依頼者の窓口が一本化
-
相続・不動産・会社法務の複合課題に強い
-
手続きと申告の同時進行で期限管理がしやすい
-
依頼後のトラブル再発防止に繋がる設計が可能
補足として、税理士司法書士の連携力は、紹介待ちの時間と情報の齟齬を抑える効果が期待できます。
限界と実務の注意点 専門性の維持や負担リスクも忘れずに
魅力がある一方で、両方の専門を高水準で維持する負担は小さくありません。税務は申告や税制改正への継続学習が不可欠で、法務は登記や戸籍収集、書類作成の正確性と期限対応が肝心です。学習と業務の両立を誤ると品質が低下し、責任範囲の見誤りも起きやすくなります。相続分野では、相続人の調査から財産の評価、遺言書の確認、申請に至るまで工程が長く、案件管理の負荷が増大します。また「税理士司法書士どっちが難しい」といった比較だけで進路を決めるのではなく、年収や将来性、独立志向、事務体制の構築などを総合で検討すべきです。兼業や両方の開業を選ぶ場合は、業務範囲の明確化と外部連携の設計で無理なく回せる体制を整えることが重要です。
| リスク領域 | 起きやすい問題 | 予防策 |
|---|---|---|
| 専門性の希薄化 | 法改正のキャッチアップ遅れ | 学習時間の固定化と分野の選択集中 |
| 期限管理 | 申告・申請の同時期集中 | カレンダー共有と進捗の可視化 |
| 品質管理 | 書類不備や説明不足 | チェックリストとレビュー導入 |
| 収益設計 | 単価のばらつき | 提供メニューと費用の明確化 |
補足として、行政書士との違いや弁護士への連携基準を事前に定めると、対応範囲の線引きがより明確になります。
行政書士や弁護士とどう違う?相談ミスを防ぐための全体マップ
行政書士との違いを一目でチェック!申請書類や許認可の使い分けポイント
相続や会社設立の相談で、税理士司法書士と行政書士のどこに依頼するか迷いがちです。行政書士は官公庁への許認可申請や各種契約書の作成が中心で、建設業許可や飲食店営業許可、内容証明の作成などに強みがあります。一方で税理士は税務申告や相続税の計算、経営や会計に関するアドバイスを担当し、司法書士は不動産登記や商業登記、相続での名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書の登記添付書類整備に対応します。相続の流れで例えると、相続財産の評価と相続税申告は税理士、相続登記や名義変更は司法書士、許認可の変更手続は行政書士が適任です。争いがなく書類と申請で完了する手続かどうかを軸に判断すると、相談の出だしで迷いにくくなります。複数の士業が連携すれば、手続の漏れを一括でカバーしやすいのもメリットです。
-
行政書士は許認可申請や契約書などの作成・提出のプロ
-
税理士は税務・申告・相続税の計算と相談のプロ
-
司法書士は登記・法務書類と名義変更のプロ
上記を組み合わせると、相続や会社設立の工程をスムーズに進めやすくなります。
弁護士との違いはここ!紛争や交渉が必要かで選択しよう
弁護士は交渉・訴訟・紛争解決の代理ができる唯一の士業です。税理士や司法書士、行政書士は、原則として裁判での代理や相手方との法的交渉の全面代理は行いません。たとえば相続で遺産分割協議がまとまらない、遺留分侵害額の請求を巡って対立がある、会社の株主間で法的紛争が発生したといったケースでは、まず弁護士への相談が安全です。合意済みで手続だけが必要な場合は、税理士が相続税の申告、司法書士が相続登記、行政書士が官公庁への変更届を担うと効率的です。紛争の有無と代理の必要性が判断軸になります。税務調査でのやり取りは税理士が対応可能ですが、重加算税や刑事手続へ発展する恐れがあるときは弁護士の出番です。相続、登記、申告などの実務と、交渉・訴訟の領域を明確に切り分けることで、初回相談のミスを最小化できます。
これで準備万全!税理士と司法書士への相談を成功させる極意
相続・登記・税務で共通!事前に揃えたい書類リスト
税理士と司法書士にスムーズに相談するなら、最初の一歩は書類の抜け漏れゼロです。相続や不動産登記、相続税の申告まで対応する場面では、本人確認から相続財産の裏付け、収支の証憑まで一式を整えるほど打ち合わせが短縮され、費用見積も正確になります。次の基本セットを起点に、案件の特性で追加しましょう。早い段階で写しを作成しておくと、両方の士業に同時提示できて便利です。
-
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、住民票)
-
戸籍一式(出生から現在まで、相続人の戸籍・除籍・改製原)
-
不動産関係(登記事項証明、固定資産評価証明、名寄帳、地積測量図)
-
金融資産(預金通帳の写し、残高証明、有価証券の取引報告書)
-
負債・ローン(借入契約書、残高証明、カード明細)
-
収支資料(源泉徴収票、確定申告書、帳簿や会計データ)
-
遺言書・遺産分割協議書の案(あれば現物、なければ意向メモ)
-
会社関連(法人登記の履歴事項全部証明、定款、株主名簿)
上記は相続・登記・税務の共通土台です。必要に応じて評価資料や見積を追加すると、依頼範囲が明確になりやすいです。
| 分類 | 主な書類 | 取得先・ポイント |
|---|---|---|
| 身分・相続人 | 戸籍・住民票 | 本籍地の市区町村、複数人分を時系列で収集 |
| 不動産 | 登記事項証明・固定資産評価 | 法務局・市区町村、地番と家屋番号を確認 |
| 金融・証券 | 残高証明・取引報告 | 各金融機関、相続発生日の残高が重要 |
| 税務・収支 | 確定申告書・帳簿 | 税務相談では直近3年分が有用 |
| 負債 | 借入契約・残高証明 | 返済予定表も合わせて提出 |
表のとおり、取得先を押さえると回収が一気に進みます。原本と写しのセットで管理すると提出が楽です。
面談で正確に希望を伝えるコツ!誤解ゼロの情報整理術
面談の質は事前整理で決まります。税理士と司法書士に同席を依頼するケースでも、目的・期限・予算・優先順位を一枚にまとめるだけで、提案の精度とスピードが上がります。特に相続では、相続人の連絡体制や意向の差が手続きの停滞要因になりやすいため、意思決定プロセスを誰がどう担うかを明確化しましょう。以下の手順で要点を固めると、誤解が起きにくくなります。
- 目的の明確化(例:不動産の名義変更を急ぐ、相続税の節税と申告期限の厳守)
- 期限の設定(登記や申告の法定期限、金融機関の対応期限を一覧化)
- 範囲と優先順位(やること・やらないことを明文化、相続と登記の順序も整理)
- 予算と支払い方法(概算の上限、実費の立替有無、見積の比較軸)
- 関係者・連絡体制(窓口担当、合意形成の手順、連絡手段と頻度)
この流れで資料と意向がそろえば、見積の比較やダブルライセンスの活用可否も判断しやすくなります。初回面談シートを用意し、更新しながら共有するのが効率的です。
よくある疑問を即解決!税理士と司法書士に関する質問まとめ
税理士と司法書士の違いは?すぐわかる役割&業務のまとめ
税務の悩みは税理士、登記や法務の手続きは司法書士が担当します。税理士は税務相談と申告の独占業務を持ち、確定申告や相続税の計算、経営のアドバイスに強みがあります。司法書士は不動産登記や商業登記の申請代理の独占業務を担い、相続人の戸籍収集、遺産分割協議書の作成サポート、会社の設立や役員変更の登記に対応します。迷ったら役割の起点で考えるのが近道です。一次判断の参照先としては、各士業の法定業務の範囲を示す公的情報が有用です。税理士と司法書士は連携しやすい職種なので、案件によっては両方に依頼する前提で進めると時間短縮になりやすいです。
-
税理士が得意なこと
- 相続税・所得税・法人税の申告と税務調査対応
- 記帳・決算・節税のアドバイスや経営相談
-
司法書士が得意なこと
- 不動産の名義変更や会社の設立・変更の登記申請
- 相続人調査や書類作成の代行と手続きの進行管理
補足として、行政書士との違いは「登記や税務の独占業務を持たない点」です。役割の線引きを理解すると依頼の初動が早くなります。
相続はまずどちらに相談する?財産状況や期限によるベストな選び方
相続は財産の中身と期限で相談先が変わります。相続税の発生見込みがある、または節税や申告が必要なら税理士に先行相談が合理的です。土地や自宅、預貯金、株式の名義変更や不動産の登記が中心なら司法書士が起点になります。どちらも関わるケースが多いため、連携でワンストップ進行できる体制を選ぶと安心です。期限面では、相続税の申告は原則10か月、名義変更は金融機関や不動産の手続きに期限や実務上の締切が伴います。次のフローを目安にしてください。
| 判断軸 | 優先相談先 | 典型的な業務 |
|---|---|---|
| 相続税が発生または不明 | 税理士 | 相続税試算、申告、節税提案 |
| 不動産や会社の名義変更 | 司法書士 | 登記申請、戸籍収集、協議書作成サポート |
| 申告と登記が同時に必要 | 税理士と司法書士の連携 | スケジュール統合、資料共有 |
-
ポイント
- 相続人や相続財産の把握が不十分な場合は、司法書士の調査力が役立ちます。
- 課税ラインの可能性があるときは、早期に税理士が概算を提示すると迷いが減ります。
以下の手順で動くとスムーズです。
- 相続人と相続財産の概況を把握し、固定資産評価や預貯金残高を整理する
- 相続税の発生見込みを税理士に確認して申告期限から逆算する
- 不動産・預貯金・有価証券の名義変更は司法書士が計画化し、登記と申告の順序を調整する
- 遺産分割協議書の内容は税理士の税務影響も踏まえて確定し、司法書士が形式要件を整える
期限を見誤らなければ、費用も時間も最小化しやすくなります。