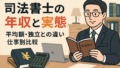「社労士に相談したいけれど、何ができるのか分からない…」と迷っていませんか?
実は、社会保険手続きだけでなく、労務管理や給与計算など幅広い業務をカバーするプロフェッショナルが社労士です。
例えば、企業の【入退社手続き】では1件ごとに平均30分以上の時間を要し、誤りが生じた場合には、行政からの指導や罰則が科されるケースもあります。近年では、労務トラブルによる訴訟は年間【7,000件】を超えて推移しており、的確な労働環境整備の必要性がますます高まっています。
さらに、年金請求や助成金申請なども専門知識がなければ手続きミスや損失につながるリスクがあります。
「どこまで社労士に相談できるの?」「費用はどれくらい?」といった疑問や不安も、今ここで一気に解消できるでしょう。
正しい知識を身につけるだけで、見えない損失や手続きミスを未然に防ぎ、余計なコストや時間の浪費をなくせます。
最後まで読むことで、あなたの会社やご自身の状況に合ったベストな活用法や、知らないと損する具体的事例も【網羅的】に知ることができます。
今こそ社労士の専門性がどれほど役立つのか、その全貌を一緒に確かめていきましょう。
社労士は何ができるのか?業務範囲と専門性の全貌解説
社労士(社会保険労務士)は企業や個人の労働・社会保険に関する手続きや管理、労務トラブルの予防や解決策のアドバイスまで幅広い分野で活躍しています。国家資格者として法令遵守のプロであり、適切な就業規則の作成や人事労務のコンサルティング、煩雑な保険申請の代行など、経営者や従業員の負担を最小限に抑える重要な役割を担います。
キャリアの選択肢として目指す人が多い一方、「仕事がない」「やめとけ」などのネガティブな再検索ワードも一定数ありますが、専門性や人事労務の知識の高さは今後の企業課題解決や働き方改革にも大きく貢献しています。
社労士の法的独占業務とは何か – 1号・2号業務の範囲や意義を具体的に解説
社労士の業務は「独占業務」と呼ばれる範囲が法律で明確に定められています。これらは国家資格を持つ社労士にしか認められていない業務で、企業が正しく社会保険や労働基準法等を遵守するための重要な部分です。
下記は主な独占業務一覧です。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号業務 | 労働・社会保険諸法令に関わる申請手続等の代行 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の各種申請 |
| 2号業務 | 帳簿書類の作成及び提出代行 | 労働者名簿・賃金台帳・就業規則等の作成・提出 |
独占業務の意義は、専門的でミスの許されない手続や書類を、経験・知識豊富な第三者が正確かつ迅速に対応する点にあります。罰則やトラブル回避のためにも、社労士の存在が欠かせません。
1号業務の詳細解説と具体的手続き例 – 健康保険・労働保険・年金など申請手続き等の流れ
1号業務とは、事業所や従業員に関わる健康保険や厚生年金、労働保険などの申請・届出・各種変更手続きを、社労士が代理人として行うことを指します。
申請の流れ(例:労働保険の年度更新)
- 必要書類の準備と入手
- 保険料の算出や書類記入
- 行政機関への電子申請・書類提出
- 控え・証明書取得・保管
主な手続き例
-
新規法人設立時の社会保険適用手続き
-
従業員入退社時の雇用保険加入・喪失手続き
-
災害発生時の労災保険給付申請
-
年金事務所への届出や電子申請
素早く正確に処理することで、企業のリスクやトラブルを防ぎます。
2号業務での書類作成と管理業務解説 – 労働者名簿や賃金台帳、就業規則作成などの書類整備
2号業務とは、労務管理や労働法に基づく法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳など)の作成や、就業規則の新規作成・改定を行う業務です。労働基準監督署や年金事務所などへの提出も含まれます。
主な書類作成・整備のポイント
-
労働者名簿:従業員の基本情報や雇用履歴を正確に記載
-
賃金台帳:給与支払いや手当、社会保険料控除を詳細に管理
-
就業規則:法改正や自社事情を踏まえたルール策定・改定
-
その他、時間外協定(36協定)や雇用契約書の整備も
実務上は、これらの整備が不十分だと行政指導・監督やトラブル時の証明責任で大きな不利益を被ることもあります。社労士は、法的リスク対策の観点からも大きな信頼につながります。
3号業務:コンサルティングと労務管理サポートの広がり – 人事労務に関する助言や問題解決支援
3号業務は、個別の手続きや書類作成だけでなく、「労務管理全般の相談・助言」「制度設計」「現状診断」などコンサルティング業務を幅広くカバーします。
働き方改革・人事制度設計・評価制度の導入支援・ハラスメント対策など、人事労務にまつわる課題全般でのアドバイスも含まれます。
サポート事例
-
労使紛争・トラブルの予防、解決案の提示
-
社員のエンゲージメント向上や離職防止のための施策
-
テレワーク導入など実務運用に即したルール作り
社労士は、企業の経営に寄り添いながら、専門知識と実務経験を活かして成長をサポートします。今後もAIや制度改革の波の中で、柔軟性と専門性が問われる場面が増加しています。
労務トラブル予防と働き方改革支援の実態 – 労働環境改善や法改正、リスク管理支援
昨今、働き方改革や法改正の加速により、企業と社員それぞれが新たな対応を求められています。社労士は、「未払い残業代トラブル」や「解雇・退職勧奨時の法的リスク対策」など、予防から解決まで一貫したサポートを提供。
代表的な支援内容
-
法改正への迅速な就業規則の見直し
-
時代に即したテレワーク勤務規定やメンタルヘルス対策
-
労働紛争や行政指導時の事実関係整理と対応策の提案
-
個人の年金や保険制度・退職金等に関する相談対応
正確な知識と柔軟な実行力で、複雑な労務問題から企業の健全な発展を守ります。
社労士に依頼できる具体的業務一覧と利用のメリット
企業が依頼できる事例と効果的活用法 – 給与計算、助成金申請、就業規則作成など企業課題ごとの活用
企業が社会保険労務士に依頼できる業務は多岐にわたります。特に、給与計算や社会・労働保険の各種手続きの代行、助成金申請のサポート、就業規則の作成・改定などは、専門的な知識が求められる重要な分野です。複雑な法改正にも素早く対応できるため、コンプライアンス強化や人事部門の負担軽減にもつながります。
法人によくある課題と社労士活用の例をまとめました。
| 課題 | 社労士ができること | 利用メリット |
|---|---|---|
| 従業員の社会保険加入・脱退 | 手続き一式を専門家が代行 | ミス防止・工数削減 |
| 給与計算の負担が大きい | 毎月の給与・賞与計算を正確に処理 | 作業効率化・リスク軽減 |
| 法改正への対応に不安 | 最新の法制度に基づき規則作成・改定を支援 | 企業リスクの最小化 |
| 助成金情報を知らずに損をしている | 条件に応じた助成金申請のサポート・アドバイス | 経費負担の低減・機会損失の回避 |
専門家による支援を活用することで、法令対応ミスのリスクや人的ミスを大幅に減らし、無駄なコストも削減できます。また、近年は労働法改正や働き方改革への対応も必須となっており、社会保険労務士のサポートは経営の安定に直結します。
個人が相談可能な社会保険・労働問題の支援 – 年金相談、解雇問題、労働手続きサポート
個人が社会保険労務士に依頼できることも多くあります。年金相談や適切な請求手続き、解雇や労働条件のトラブル対応、さらには出産・育児・介護休業などライフイベントに関する各種申請のサポートまでカバーします。「社会保険労務士に相談できることは企業向けだけ」と思われがちですが、個人の生活やキャリアにも密接に関わっています。
個人がよく相談する代表的なケースをまとめています。
| 相談内容 | 社労士による支援 |
|---|---|
| 年金の受給・請求手続き | 必要書類の案内・申請サポート |
| 解雇や退職時のトラブル相談 | 法律面のアドバイス・交渉サポート |
| 労働時間・残業代の未払い問題 | 権利確認・申請手続きの支援 |
| 各種保険(健康・失業・育児・介護) | 必要な手続き方法・制度利用のアドバイス |
社会保険や労働問題で迷ったとき、社労士なら的確なアドバイスを受けられます。専門家のサポートを受けることで、複雑な制度や申請手続きに安心して臨むことができ、将来設計やトラブル解決の大きな助けになります。
他の士業との違いと役割分担:社労士だからできること
士業それぞれの専門領域と業務範囲概要 – 各士業の法定業務と社労士の業務比較
様々な国家資格を持つ士業の中でも、社労士(社会保険労務士)は労働・社会保険分野に特化した専門家として独自の役割を担っています。他の代表的な士業と社労士の業務範囲を比較することで、社労士だから対応できる領域が鮮明になります。
| 資格 | 主な業務範囲 | 法定独占業務の主な内容 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 労働・社会保険の手続き全般、就業規則作成、給与計算、労務管理、企業の人事コンサルティング | 社会保険・労働保険の手続き代行/帳簿書類作成/労使関係の助言 |
| 行政書士 | 官公署への書類作成・提出、許認可申請、契約書作成等 | 許認可申請・各種法定文書の作成・提出 |
| 税理士 | 税務申告・納税代理、会計帳簿作成、税務相談 | 税務書類の作成・申告代理 |
| 弁護士 | 法律相談、裁判代理、契約・トラブルの法的対応 | 訴訟代理、法律事務全般 |
ポイント
-
社労士は社会保険や労務に関する各種手続き・相談が専門。他士業では対応不可な企業の人事・労務問題の相談や制度導入支援が強みです。
-
行政書士や税理士では社会保険・労働保険の申請や人事労務管理には直接対応できません。
-
弁護士は裁判や法的トラブル解決が専門ですが、日常的な労務管理や就業規則策定は社労士の範疇とされています。
このように、制度設計や従業員の働き方・労務トラブル回避に関しては社労士の知識と実務経験が大きな力になります。企業の「人」に関する課題をサポートできる士業は社労士だけです。
違反リスク回避のための正しい依頼判断基準 – 無資格者違反や条例順守の指針
労働・社会保険手続きや労務管理を外部委託する際は、依頼先の資格と業務範囲の確認が必須です。無資格者による手続きや証明書類の作成・提出は法律違反となり、企業にもペナルティリスクが及びます。
依頼時に必ず確認すべきポイント
- 依頼内容が社労士独占業務(社会保険・労働保険の書類作成や提出代行)に該当するか。
- 受託者が有資格の社会保険労務士か、または社労士事務所であるか。
- 料金の明確化、業務内容・守秘義務契約の有無。
- 万が一法違反が発覚した場合の補償体制。
特に社労士以外の代行業者や無資格者へ委託してしまうと、労務トラブルや行政指導に発展する危険性があります。
依頼先を選ぶ際は、社労士登録番号の有無や所属団体の確認もしましょう。不明点は必ず直接相談し、重要な書類作成や手続きは専門家である社労士へ依頼することが、安心・安全の第一歩です。
社労士の業務内容と現場実態:1日のスケジュールと働き方
社会保険労務士は、企業や個人事業主の労務・社会保険に関する幅広い業務を担当しています。その働き方は「独立開業」と「企業内勤務」に大きく分けられ、どちらも高い専門性と調整力が求められます。ここでは現場のリアルな業務内容やスケジュールを具体的に紹介し、仕事の流れや実務のポイントを整理します。近年は法改正やデジタル化、AIの進展といった環境変化が進む中で、社労士の役割も多様化しています。
独立社労士のクライアント対応と営業活動 – 顧客開拓や助成金申請、コンサル業務の日常
独立して活動する社会保険労務士は、複数の顧客企業を担当しながら幅広い業務を並行して行います。主な1日の流れは以下の通りです。
| 時間帯 | 主な業務例 |
|---|---|
| 午前 | 書類作成、社会保険や労働保険の手続き、顧客からの相談対応 |
| 昼 | 新規顧客の開拓・打ち合わせ、助成金申請支援、営業活動 |
| 午後 | 就業規則作成・改定、社内研修やコンサルティング業務 |
| 夕方 | 記録整理、労務トラブル相談、日報入力・内省 |
主な業務内容
-
社会保険・労働保険に関する各種申請や届出の代理・代行
-
企業の顧問として就業規則や賃金制度の設計・改定をサポート
-
労務トラブルや紛争へのアドバイス、解決支援
-
助成金や補助金の申請相談
-
新規顧客向けセミナーや研修会の実施
トラブルの未然防止や課題解決力が強みであり、幅広い知識とコミュニケーション力が必須です。一方で顧客開拓や営業も自ら動く必要があるため、独自のネットワークや実績が評価されやすい傾向です。最近はAIやITツールの導入で業務効率化も進んでいます。
企業内勤務の社労士業務風景とチーム連携 – 労務管理や内部調整、専門家との連携例
企業内で働く社労士は、組織の一員として従業員の労務管理や社内制度の整備に携わります。1日の業務例としては次のようなスケジュールが一般的です。
| 時間帯 | 主な業務例 |
|---|---|
| 午前 | 勤怠・給与計算の確認、入退社の社会保険手続き |
| 昼 | 社内説明会や労働法令に関する研修・相談会 |
| 午後 | 人事部門・経営陣との制度設計や運用調整 |
| 夕方 | 労働基準監督署への対応、外部専門家(弁護士等)との連携 |
主な業務内容
-
就業規則や賃金規程等の作成・改訂
-
従業員対応(入社・退職・休職など)における社内調整
-
法改正に即した制度運用の見直し
-
内部研修やメンタルヘルス対策の企画・実施
-
労働基準監督署や年金事務所など行政機関への対応
企業規模や業種により役割は異なりますが、チームでの連携や多職種との調整が頻繁に発生します。法令遵守や正確性への意識が重要で、ミスを防ぐためのダブルチェック体制も一般的です。現在ではリモートワークやクラウドシステムも活用され、柔軟な働き方も拡大しています。
将来性と業界の変化:AIの影響と社労士の今後の役割
AIでは代替できない社労士の強み – 専門的判断やトラブル対応の重要性
近年、AI技術の進化により事務処理や一部の労務業務の自動化が進んでいます。しかし、社労士にはAIでは代替できない本質的な役割があります。労働社会保険手続きの適切な判断や、労働紛争時の現場対応など、人間ならではの専門的判断が求められる場面が数多くあります。例えば、従業員の解雇やパワーハラスメントの深刻な相談、未払い賃金が発生した際の迅速な対応は、書類作成や申請だけでなく状況分析や法律の適用経験が必要です。また、企業の就業規則の作成・見直しも、現場に即したルール設計や最新法令の解釈が不可欠です。AIによる自動化が進む一方で、複雑な労使トラブルへの解決提案や人事コンサルティングの分野は、今後も社労士の強みが活きる領域といえるでしょう。
以下の表は、AIが自動化しやすい業務と社労士にしかできない専門的領域の代表例です。
| 分類 | 具体的業務例 |
|---|---|
| AIが得意な業務 | 社会保険や雇用保険の電子申請 定型的な書類作成や給与計算 |
| 社労士が強い業務 | 労務トラブルの相談・解決支援 複雑な法改正対応 現場に即したコンサルティング |
業界の変化に伴うキャリアパスや多様な働き方 – 再教育、セカンドキャリア、働き方の多様化
社労士の業界も多様な働き方が進んでいます。従来の事務所勤務や企業内社労士だけでなく、副業・兼業の広がりやフリーランスとして独立するケースも増加傾向です。特に人生100年時代といわれる現代、再教育やセカンドキャリアへの活用が注目されています。例えば40代・50代から未経験で資格取得し、企業の人事部門や法務部、または独立開業を目指す方が増えています。
働き方の多様化ポイント
-
オンライン相談や在宅勤務を可能にする事務所も登場
-
子育てや介護と両立しやすい柔軟な案件受託
-
ベテラン社労士による後進育成やセミナー講師
また、社労士の資格は全国共通で活躍できる点も特長です。地域の中小企業支援や地方移住と組み合わせた働き方も拡大しています。人事・労務の専門家として、企業経営に深く関わる相談役やパートナー的存在が期待されています。業界の将来性は、時代の変化に合わせて多様なキャリアパスを描きやすい点にあります。
料金体系と費用の現実的な相場解説・ケース別比較
料金相場の実例と費用対効果評価 – 業務内容別料金と依頼による効果
社会保険労務士へ依頼する際の料金体系は、業務内容や契約形態で異なります。毎月の顧問契約やスポット依頼、就業規則作成など、目的ごとに相場を押さえておきましょう。
以下は主な業務別の料金相場です。
| 業務内容 | 料金の目安 |
|---|---|
| 顧問契約(月額) | 20,000〜50,000円 |
| スポット相談 | 10,000〜30,000円/1回 |
| 労働・社会保険手続き代行 | 10,000〜30,000円/書類1セット |
| 就業規則作成・見直し | 80,000〜200,000円 |
| 給与計算 | 1,000〜2,000円/社員1人あたり |
| 助成金申請支援 | 受給額の10%〜20%が一般的 |
※地域や事務所の規模、従業員数、業務量で変動
費用対効果のポイント
-
社労士を活用することで、法令違反リスクや手続きミスを回避し、経営者・総務担当者の業務負担を大きく減らせます。
-
助成金・補助金申請や労働トラブル予防に有効であり、中長期的なコスト削減や企業価値向上に寄与します。
依頼先選定時の注意点や料金トラブル予防策 – 費用内訳や契約前の確認点
社労士への依頼時は、料金体系や契約条件の明確化が必要です。思わぬ追加費用やトラブルを防ぐため、事前確認を徹底しましょう。
注意したいポイント
-
業務範囲と料金を必ず文書で事前確認
-
見積書・契約書で基本料金・追加料金・オプションを明確化
-
顧問契約の場合、月額に含まれる業務内容を詳細に確認
料金トラブル予防策
-
スポット依頼では、処理すべき書類や手続き数、納期を明確に
-
着手金・成果報酬・返金規定の有無を必ず確認
-
契約前に複数の社労士・事務所から見積もりを取得し比較する
一覧にまとめると、次のような確認事項が重要です。
| 確認事項 | 具体的な確認例 |
|---|---|
| サービス範囲 | どこからどこまで社労士が担当するか |
| 基本料金・追加料金 | 手続きや社員数の増・減で料金がどう変わるか |
| 支払いタイミング | 月末締め/都度請求/成果発生時 |
| キャンセル規定 | キャンセル時の費用が発生するか否 |
| トラブル対応 | 万一のとき連絡窓口や対応方針 |
信頼できる社労士選びのために、契約前の打合せや料金説明で不明点があれば必ず質問し、納得した上で委託を進めてください。
社労士資格取得の全プロセス・試験概要と合格戦略
社労士試験の仕組みと出題傾向分析 – 試験科目や難易度、出題範囲を深掘り
社会保険労務士試験は、労働・社会保険に関する豊富な知識が求められる国家資格試験です。主な試験科目は下記の通りです。
| 試験科目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 労働基準法、労災保険法 | 労働契約や労働災害など、企業労務の基礎を問う |
| 雇用保険法、健康保険法 | 雇用・社会保険の仕組みや各制度の適用範囲を把握 |
| 厚生年金保険法、国民年金法 | 年金制度の詳細や手続きの知識が問われる |
| 労務管理その他の労働・社会保険関係法令 | 法改正にも即応した幅広い知識が必須 |
問題形式は選択式と択一式の2パターンで、広範な法律知識と条文理解、制度の実務知識が問われます。合格率は毎年6~8%前後と低い水準で推移しており、難易度の高さが特長です。出題傾向としては、最新の法改正が反映されやすく、単なる暗記では対応しきれない点がポイントです。過去問分析だけでなく、実務や法体系を立体的に理解する力が求められます。
未経験者が合格を目指す勉強計画と効果的学習法 – 働きながらの勉強法や教材選定、体験談
未経験からでも社労士試験に合格するためには、計画的な学習スケジュールと効率的なインプットが不可欠です。社会人や仕事と両立する方には、以下の学習戦略が効果的です。
-
無理のない長期スケジュール設定
- 1日1~2時間、週10時間程度の勉強時間を確保
- 年間を通じて計画的に進めることで挫折を防ぐ
-
信頼できるテキスト・問題集の活用
- 最新の法改正に対応した教材を選ぶ
- テキスト+過去問セットで反復学習を重視
-
アウトプット中心の学習
- インプット後はすぐに問題演習を繰り返す
- 模試や過去問で自分の弱点を客観的に可視化
特に忙しい方には、移動時間やスキマ時間にスマホでオンライン講座や解説動画を活用する方法も有効です。独学が不安な場合は通信講座や個別サポートのあるスクール利用も検討できます。未経験から合格した受験者の多くは「理解できない箇所は専門家に質問・相談」「自分に合う勉強法を早期に確立」したことを成功の要因と挙げています。着実な積み重ねと最新情報のアップデートが合格への鍵となります。
社労士にまつわるよくある質問と不安解消Q&A
質問例:社労士にしかできない仕事は何か? – 業務範囲や実例
社労士は法律で定められた「独占業務」を担います。主に労働保険や社会保険の書類作成・提出、労務問題に対するアドバイスなどが該当し、これらは社労士以外が行うと違法となるケースもあります。例えば、雇用保険や健康保険、厚生年金保険の手続き、就業規則の作成・変更、労働基準監督署への申請代行などは社労士の専門領域です。
下記のような業務が代表的です。
| 業務内容 | 他士業との違い |
|---|---|
| 社会保険・労働保険手続き | 社労士のみが代行可能で、書類の作成から提出まで一貫して対応 |
| 就業規則作成・見直し | 労働契約法やその他法改正に則った専門的なチェックと修正が可能 |
| 労使トラブル対応 | あっせん代理等も対応可能(特定社会保険労務士の場合)一般の相談も広くカバー |
労働社会保険の事務に特化し、企業や個人の働き方改革を根本から支援します。
質問例:社労士の収入や将来性はどうか? – 統計や今後の展望
社労士の年収は実務経験や就業形態により異なりますが、法人勤務での平均年収は400万〜600万円が多く、独立開業の場合700万円を超えるケースもあります。働き方や規模によっては大きく変動しますが、労働関係法令の複雑化や働き方改革の推進により、今後の需要増加が見込まれています。
| 職種 | 年収目安(万円) | コメント |
|---|---|---|
| 法人勤務社労士 | 400〜600 | 安定した収入・福利厚生が魅力 |
| 独立開業社労士 | 700〜1000 | 顧客開拓力次第で上限は大きく広がる |
| パートタイマー | 200〜300 | 時短勤務や副業にも対応可能 |
今後AIやIT化が進んでも「人と人の労務問題解決」や「法令遵守の実務」は残るため、社会保険労務士の役割がすぐになくなる心配はありません。
質問例:未経験でも社労士を目指せるか? – 試験やキャリアに関するアドバイス
未経験からでも社労士を目指すことは十分可能です。受験資格は「学歴」や「実務経験」など複数あり、働きながら独学や通学講座で合格を目指す人も多くいます。試験は国家資格の中でも難易度が高めですが、合格後は法人の人事部門、社会保険労務士事務所など多彩なキャリアが広がります。
- 受験資格:大学卒・短大卒・一定の実務経験など
- 試験内容:労働基準法、社会保険法、実務知識など幅広い
- キャリア:企業内社労士、独立開業、コンサルティング部門など
40代未経験やセカンドキャリアとして挑戦する方も増えており、人生を変える新しい道として注目されています。
質問例:社労士に相談すべきタイミングは? – 状況別メリットや注意点
社労士に相談する目安は、次のような場合です。
-
社会保険や労働保険の手続きに不安がある
-
就業規則や賃金規定の見直しを検討している
-
従業員とのトラブルや紛争が発生・懸念される
-
人事や働き方制度の整備・助成金申請をしたい
専門家の視点から法令適合やリスク回避のアドバイスをもらえる点が大きなメリットです。法人だけでなく個人でも、年金や雇用保険に関する困りごとがあれば早めの相談が推奨されます。相談は無料の場合や、初回のみ低価格で受けられる事務所も少なくありません。
質問例:社労士と他士業の違いを教えてほしい – 士業比較と選び方
社労士は労務・社会保険手続き、就業規則や年金関連など「人」に係る分野に特化しています。他士業との主な違いは下記の通りです。
| 士業 | 得意な業務内容 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 労働・社会保険の手続き、労務相談 | 労働法や社会保険に関する実務全般 |
| 行政書士 | 官公庁への各種申請書類作成 | 会社設立や許認可申請等の書類作り |
| 税理士 | 税金計算、確定申告 | 税務申告・会計業務全般 |
| 弁護士 | 裁判や法律相談全般 | 労使紛争、法廷代理人 |
何を相談したいのかによって選ぶ士業が異なります。労務の管理や社会保険の複雑な手続きは、社労士への相談が最適です。各士業の特徴と自社の課題を照らし合わせて、最適な専門家を選びましょう。